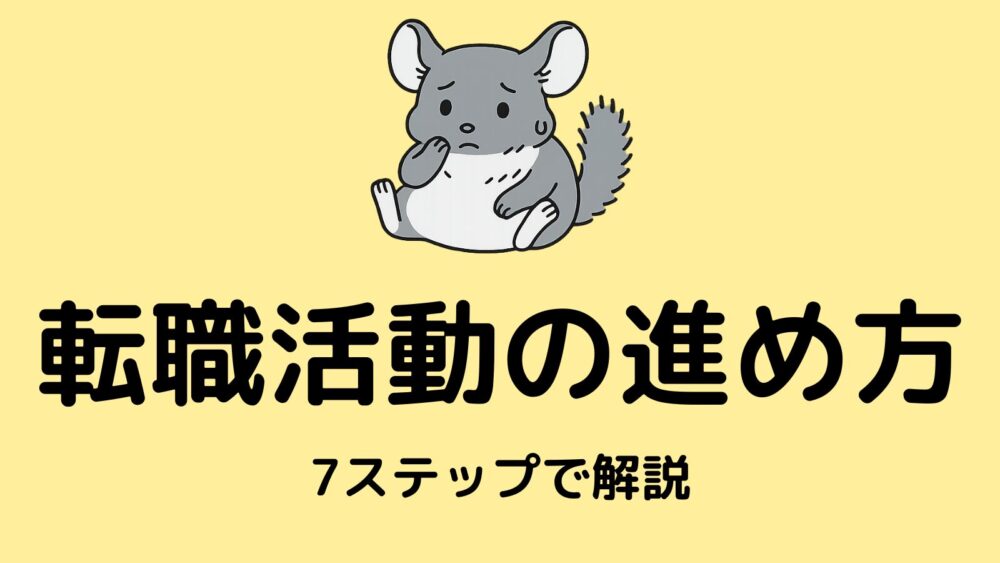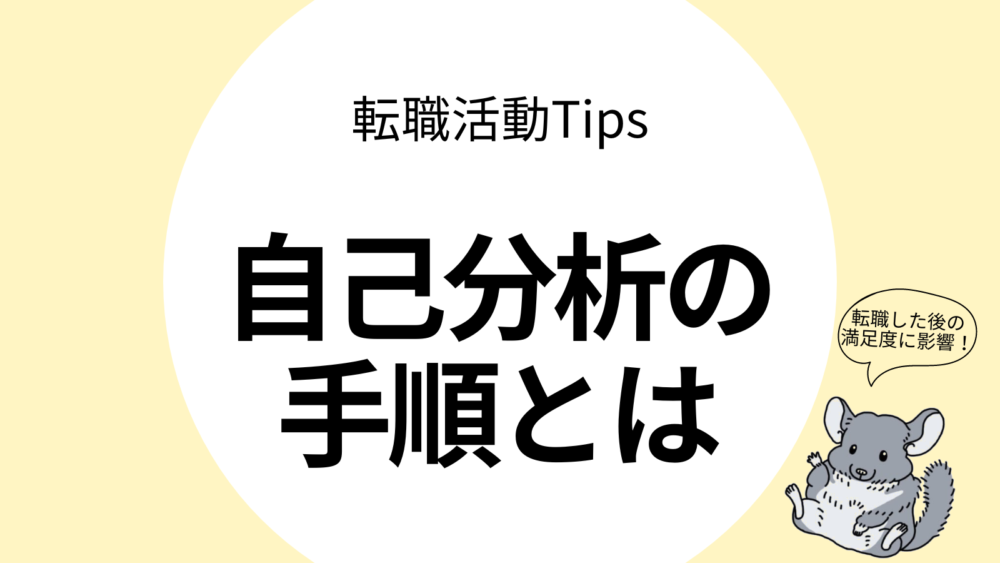- 今の仕事、自分に合ってない気がする
- このまま働き続けていいのか、漠然と不安
- 転職も考えてるけど、自信が持てない…
発達障害がある私たちにとって、「自分に合った働き方」は分かりにくいもの。少しだけでも時間を取って、自己分析から始めてみましょう。
しかし実際は、「自己分析って何から始めたらいいの?」と悩む人は多いです。
 よしだ
よしだ現在地が分からないと迷子になるよ!




本記事では発達障害のある方が「自分に合った働き方」を見つけるための、自己分析の進め方を紹介します。
自己分析では、スタート(現状)とゴール(目指す方向)を言葉にすることが目的。自分の得意なことや苦手なこと、過去の経験などを整理すると、これからの進路を決めるヒントにもなります。
本格的に応募を始める前に、自己分析で方針を明確にしましょう。
- 自分に向いてる働き方ってなんだろう?
- 今のままで将来は大丈夫かな?
そんな方は本記事を、ぜひ最後までお読みください。
発達障害者こそ現状の整理に自己分析が必要


発達障害のある方が仕事や働き方を見直す場合、動き出す前に自己分析が必要になります。
自己分析とは、スタート(現状)とゴール(目指す方向)をはっきりさせる作業。頭の中でぼんやり考えていることを整理し、言葉にすることが目的です。
「働きやすさ」の例)
- 配慮を受けながら落ち着いて働けること
- 頑張ったぶんだけ評価に反映されること
- スケジュールやタスクに縛られないこと
「働きやすさ」は人それぞれ。発達障害の特性も、人によって大きく異なります。
一般化された「働きやすさ」ではなく、自分にとって働きやすい基準を言葉にすることが大切です。
あなたの現状と目指す方向を自己分析で整理し、納得できる方針を言葉に落とし込みましょう。



あくまで「自分にとって」のスタートとゴールを決めよう!
自己分析で整理したい3つの目的


自己分析をする目的は、「やりたいこと(Will)」「できること(Can)」「求められること(Must)」の3つの視点で整理すること。
Will・Can・Mustのバランスが取れると、仕事選びや働き方に納得感が得やすくなります。
「Will Can Must」とは、Will(やりたいこと)・Can(できること)・Must(すべきこと)の3つから、仕事での目標設定やキャリア分析を行うフレームワークです。
引用:人材アセスメントラボ(miidas)
自己分析の具体的な手順へ進む前に、目的を把握しておくのがオススメです。



欠けたところから不満が出やすくなるよ!
やりたいこと(興味や価値観)
「やりたいこと」を整理するのは、あなたが前向きに日々を過ごすモチベーションを発掘するための視点です。
- どんな仕事や環境なら心地よく続けられるか
- どんな時に楽しさや充実感を感じられるか
- 自分は働くことで何を得たいのか
他人の価値観や社会の目に流されず、自分らしい選択ができるようになります。「やりたいこと」が明確になるほど、働く意欲や満足度も自然と高まります。
自己分析を進めるなかで、小さな興味や「これだけは譲れない」と思うことを見つけてみてください。
自己分析で見つけた興味や価値観が、あなたらしい働き方や居場所を選ぶ判断基準になります。
できること(スキルや経験)
「できること」を整理するのは、キャリアや今後の働き方を組み立てるための視点です。
自分がどんな仕事や作業を続けてきたか、どんなスキルや知識を持っているかを整理することで、本来の強みや活躍できる場面が見えてきます。
- 業務で評価された経験
- 資格や訓練で身につけたスキル
- 自分にとって「当たり前」にできること
「できること」が分かると、自信をもってこれから進む方向を選べます。自分に合わない選択肢を避けやすくなり、納得感のある決断ができます。
たとえ今は「できること」が少なくとも、徐々に増やしていけば将来の可能性にもつながるでしょう。
求められること(社会・職場のニーズ)
「求められること」を考えるのは、社会や職場の期待と自分の特性・強みが重なるポイントを見つけるため。
どうすれば適切な評価を受けられるかという視点も、働くうえでは重要です。
- 企業や職場が必要とするスキルや姿勢を整理してみる
- 自分の特性や経験が、どんな場面で役立つかを考える
- 世の中で評価される場面と、自分の持ち味が重なる接点を探す
自分ひとりの納得感だけでなく、周囲からも必要とされる役割を見つけることで、「社会とつながる安心感」や「評価されやすい働き方」が見えてきます。
自分に何ができて、どんな場面で活かせそうか?を意識することで、現実的な選択肢や納得感のある働き方につながります。
自己分析の進め方:4つの手順


自己分析は、おおまかに分けて以下4つの手順で進めます。
- キャリアの棚卸しをする
- 強み・弱みを整理する
- 発達障害の特性を理解する
- 希望条件を洗い出しキャリアの「軸」を明確にする
自己分析は自分の内面と向き合う作業、少し進めるだけで疲れてしまう場合もあります。
焦ってすぐに終わらせようとせず、時間を取ってじっくり取り組んでみてください。
グレーゾーンの方やクローズ就労を目指す方でも、基本的に自己分析の手順は同じです。強みや弱みはもちろんのこと、特性の傾向を把握しておくだけでも「働きやすさ」へのアプローチが変わります。



自己分析は今後の方針を決める大事なステップだよ!
キャリアの棚卸しをする
「キャリアの棚卸し」は自分の過去を客観的に振り返り、経験と価値観を整理する作業です。
ただ職務経歴を並べるのではなく、その時どんな気持ちだったか、何を学んだかも一緒に書き出しましょう。
「事実と感情」を分けて見える化すると、自分の強み・弱みや働きやすさの根拠がわかり、納得感のある選択につなげやすくなります。
- 過去の客観的な「事実」をすべて書き出す
- 書き出した事実に「感情」を追記する
- 共通パターンを見つけ「得意・苦手」を言語化する
- 仕事で得られたスキル・能力を見つける
- 分析結果からキャリアの方針を決める
棚卸しで見つけたパターンや共通点が、「自分に合う働き方」や「今後の方針」の判断材料になります。
キャリアの棚卸しは転職の準備だけでなく、現状維持や環境を整える際にも使える土台の部分。丁寧に整理すればするほど、後の自己分析も進めやすくなります。
一気に完璧を目指さず、少しずつ進めましょう。
キャリアの棚卸しについての詳細は、以下の記事をお読みください。
強み・弱みを整理する
自分の「強み・弱み」は、過去の経験や他人の意見も参考にしながら、具体的なエピソードと合わせて整理しましょう。
同じ特徴でも、置かれる環境によって、強みにも弱みにもなります。どんな場面でプラスに発揮されるか(マイナスになったか)も書き出してみてください。
強みの探し方
- 成功体験を振り返る
- 好きなことを書き出す
- 没頭した経験を思い出す
弱みの探し方
- 失敗経験を分析する
- 家族や知人の意見を聞く
- 共感したSNSの投稿からヒントを得る
整理した強みや弱みは、そのまま仕事選びや働き方の判断材料に活かせます。
たとえば「強み」は職種選びや自己PRに、「弱み」は配慮やサポートを求める際の根拠として使えます。
詳細な手順や実例については、以下の記事も参考にしてください。
発達障害の特性を理解する
発達障害がある人にとって、「特性を理解する」ことは欠かせないポイント。どんな配慮や工夫が必要かを整理しておけば、働くうえでつまづきやすい点を把握できます。
発達障害の特性は一人ひとり異なるため、まずは以下を書き出してみてください。
- 何が問題になりやすいか
- どのように対処してきたか
- どんなサポートや配慮があれば働きやすいか
「こんな配慮があれば力が発揮できます」と伝えられれば、企業側は配慮の検討がしやすくなります。苦手なことや弱みは、工夫やサポートでカバーしましょう。
一方で、自分の得意なことや強みにも目を向けて、職場でどう活かせるか考えることも大切です。
詳しい整理方法や考え方については、以下の記事も参考にしてください。
希望条件を洗い出しキャリアの「軸」を明確にする
自分に合った働き方やキャリアを実現するためには、最初に「働きやすさ・続けやすさ」を左右する条件をリストアップしましょう。
- 業務内容
- 働く時間
- 職場環境 など
紙やスマートフォンのメモアプリへ、思いつくまま書き出してみてください。
そのうえで、条件の中から「絶対にこれだけは譲れない」と思える要素を1~3個に絞り、今後のキャリア選択の「軸」として定めるのがポイントです。
「軸」があれば転職だけでなく、働き方を見直したいときや資格取得、副業・独立を考えるときにも判断に迷いにくくなります。



私は「在宅勤務×副業OK」を絶対条件にしてたよ!
自分に合った働き方を実現するため、ぜひ「希望条件の洗い出し」と「軸」の明確化に取り組んでみましょう。
試しに一度メモアプリへ書いてみるだけでも、新しい発見があります。
キャリアの「軸」を整理する具体的な方法については、以下の記事を参考にしてください。


発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?
- 自己分析が進まない → 自分の強みが分からない
- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない
- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配
こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼りましょう!
- 書類添削+面接対策で合格率UP
- 特性に合う求人を一緒に選べる
- 日程調整や企業とのやりとりを代行
もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?



方向性の相談だけでもOK。初めてなら「dodaチャレンジ」がオススメだよ!
\ 発達障害の当事者が厳選! /
自己分析に取り組むときの心構え
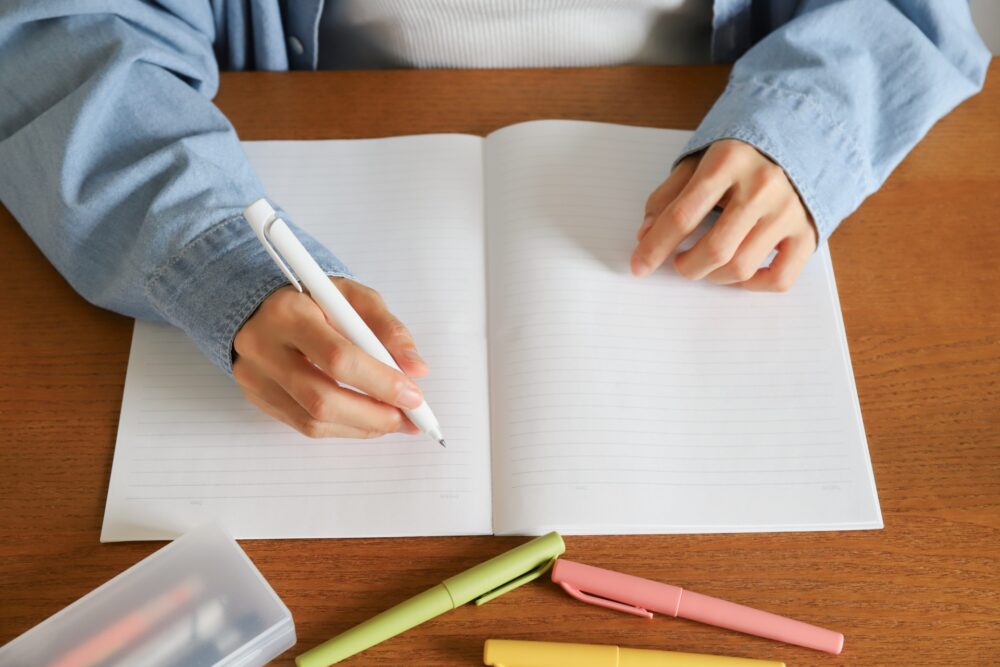
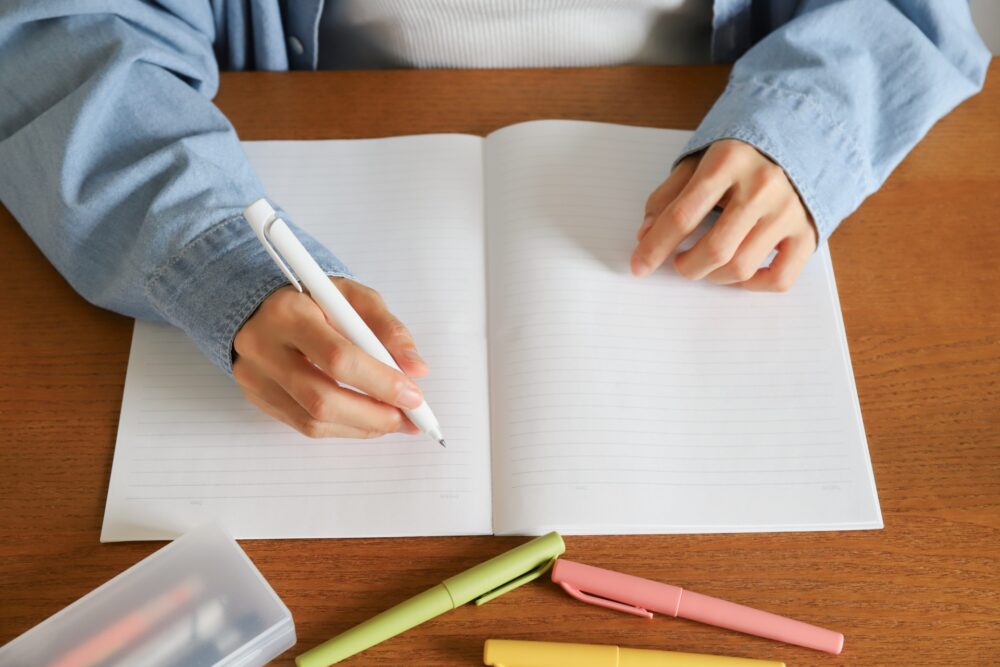
自己分析をいきなり完璧にやろうとすると、かえって手が止まってしまう人もいます。
大切なのは「少しずつやってみる」こと。自己分析に気軽に取り組むコツや、挫折しないための考え方を紹介します。



内面と向き合う作業はしんどい!少しずつやろう。
完璧を目指さず、まずは書き出す
自己分析に取り組むとき、「綺麗にまとめないと」「正しい答えを出さなきゃ」と意識しすぎる人は多いです。
しかし、最初から完璧な形にする必要はありません。それよりも「思いついたことを片っ端から書き出していく」ことの方が大切です。
頭の中で考えているだけだと、整理するのは難しいもの。紙やスマートフォンのメモアプリなどを使って、頭の中から外へどんどん出してみましょう。
書き出すときの例)
- 営業職3年くらい
- 単語だけ(商品名や会社名など)
- 思いついたままの文章(見積書を作ったときに褒められた。など)
綺麗にまとめるのは、書けることがなくなってきてからでもOK。デジタルならコピー&ペースト、紙なら矢印を引いたり丸で囲ったりするのも良いでしょう。
一回の自己分析で結論を出さず、定期的に繰り返してみるのも有効です。何度か見直していくうちに、新しい発見が見つかることもあります。
他人との比較より自分の変化に注目する
自己分析をしていると、「他の人に比べて自分は…」と考えてしまうことがあります。しかし、他人と比較するよりも、自分の変化に注目してください。
自己分析で大事なのは「以前の自分と比べてどう変わったか」「これからどうするか」という視点です。
たとえ小さなことでも、以下のような変化に目を向けましょう。
- 昔よりも会議で発言できるようになった
- タスク管理がスムーズにできる日が増えた
- 困ったときに人に相談できるようになった
自己分析はスタート(現状)とゴール(目指す方向)が大切。他者の良いところや強みに引っ張られず、自分自身の方針を定めましょう。
「できるようになったこと」を積み重ねることも、今後の働き方を見直すポイントにもなります。
「正解」よりも自分の納得感を大事にする
自己分析を進めていくと、「これが正解なのかな?」と迷うことがよくあります。
しかし、必要なのは最もらしい正解よりも自分の納得感。いろいろと考えた結果、自分なりに「この方向でやってみたい」と思えたら、自己分析の十分な成果です。
- 得意な業務の傾向が見えた
- 苦手な環境がはっきりした
- やってみたいことが見つかった
納得のいく方針があれば、次に動き出すきっかけとなります。
逆に「一般的な理想像に自分を合わせよう」としすぎると、かえって動けなくなる人は多いです。その結果、モチベーションが続かず、立ち止まってしまいます。
私の場合は「営業職の転職先は営業職が多い」という一般論から、合わない営業職をずっと続けた経験があります。自己分析で「それよりも裏方でコツコツ」「モノづくりの方が合うかも」といった仮説が出てきたため、そこから営業職のループを抜け出せました。
「今後どうしていくか?」といった大きな課題には、自分で見つけた納得感が大切になります。
自己分析がうまくできないときの対処法


自己分析に取り組んでみたものの、うまく整理ができないと感じることがあります。自分のことを客観的に分析するのが苦手な人もいるでしょう。
行き詰まったときは無理に進めようとせず、一度休んだり、別の方法を試してみるのも有効です。
- マインドマップに頭の中の言葉を書き出す
- 自己分析ツールの診断からヒントを探す
- 関連書籍や他人の経験談からヒントをもらう
やり方や視点を変えることで、考えが整理されることもあります。
自己分析がうまくいかないのは、「向いていないから」ではありません。少しやり方を変えるだけで、整理が進むことも多いです。
自己分析が進まずに困っている方は、以下の記事も参考にしてみてください。



「自己分析」を更に細分化するのもオススメ!
自己分析をより深めるためのポイント


自己分析では、主観的な視点と客観的な視点の両方が大切です。自分で考えた結果と客観的な見え方を比べることで、より立体的な分析ができます。



主観と客観で印象が変わることもあるよ。
ツールの診断結果と自分の考えを比較する
自己分析を進めたあとに自己分析ツールも併用し、自分の考えとの違いを比較してみるのが特にオススメです。
自己分析はどうしても主観が入りやすいもの。ツールの診断結果という「外からの視点」を取り入れると、新しい発見や意外な気づきが得られます。
- 自分では弱みだと思っていた部分が実は強みにもなる
- 苦手だと思い込んでいた分野に適性が見つかる
- 無意識だった強みが客観的に可視化される
こうしたギャップを確認することで、より深い自己理解が可能です。認識とのズレがなかった場合でも、「自分で決めた方針」に更に自信が持てます。
ツールと自分の考えの、どちらが正しいかではありません。「自己分析で感じた自分像」と「ツールの結果」を見比べてみること自体に価値があります。
気づきや納得感につながるヒントとして、まずはひとつ試しに自己分析ツールを使ってみましょう。
第三者の視点を取り入れる
自己分析はどうしても一人で考える時間が長くなりがちです。その分、自分だけの視点に偏ってしまうこともあります。
客観的な意見を聞くため、第三者に話してみるのも効果的。家族や友人、同僚、支援者など、他者から見た自分の印象を聞くだけでも、新しい気づきが生まれることがあります。
- 自分では「当たり前」だが他者から見たらすごいこと
- 一人だと思いつかなかった価値観や工夫
- 自分の思い込みや思考の癖
一人でじっくり考えるのも大切ですが、「他人の目線」を取り入れることで、より客観的な自己理解につながります。
相談相手が見つからないときは、生成AIなどに相談するのも一つの方法です。
転職を視野に入れている人であれば、「転職エージェント」からプロ視点で意見をもらうのもOK。
自分自身の解像度を上げるために、第三者の視点を取り入れてみてください。
定期的に見直す習慣を持つ
自己分析は「一度やって終わり」ではなく、定期的に見直して更新していくことが大切です。
働く環境や経験が変われば、できることや考え方も変化していきます。昔の分析結果や価値観を引きずってしまうと、今の自分に合わない選択をしてしまうかもしれません。
- 以前よりできることが増えている
- 苦手意識が薄れてきた
- 興味や価値観が変わってきた
- 新しい「やってみたいこと」が出てきた
こうした変化をきちんと反映していくことで、より納得感のあるキャリア選択につながります。
見直すタイミングは「半年に1回」や「誕生日・年末年始」など、自分なりにルールを作ってみると良いでしょう。
大がかりな自己分析ではなく、過去の分析結果を読み返したり、気付いたことをメモに追記したりするだけでも十分。前回からの変化を確認しながら、少しずつ続けていくことがポイントです。
自己分析は「やったら終わり」ではなく定点観測。定期的に振り返る習慣を作ってみましょう。
発達障害者が自己分析をするメリット


発達障害者の自己分析は「自分を知るため」だけでなく、より働きやすく納得感のあるキャリアを作る土台になります。
得意なことや苦手なことがはっきりしたり、他者に自分の特徴を伝えられるようになったりと効果大。行動に自信が持てるのは、不安を抱えやすい私たちにとって大きなメリットです。



モヤモヤを抱えてる人ほど自己分析がオススメ!
得意・不得意を明確にして働きやすさを高める
自己分析で自分の得意・不得意を明確にしておくことは、働きやすさや職場での安定感を高めるうえで特に役立ちます。
私たちの場合は「得意・不得意」の差が出やすいため、得意な仕事や苦手な環境の見極めが大切。具体的に言語化できていれば、特性によるアクシデントも起きにくくなります。
- 苦手な業務にはサポートを求める
- 評価を得やすい仕事に注力する
- 無理しすぎない働き方を設計する
たとえば不得意な作業や環境が分かっていれば、求人選びや配属時にミスマッチを防げたり、必要な配慮をスムーズに伝えられます。
逆に得意なことがはっきりすれば、成果を出しやすい環境や役割を狙った方向転換も可能です。
「得意・不得意」を自己分析することは、働きやすい環境を作るための材料になります。
自分のことをうまく言語化できるようになる
自己分析を進めていくと、自分の特徴や考え方を言葉にして伝える力が少しずつ身についてきます。
私たちの場合、「どういう配慮が必要なのか」「どんな場面で困りやすいのか」など、自分自身で説明する場面は多いです。自分の言葉で説明できる能力は、職場や上司、同僚といった第三者の理解度に直結します。
- 面接や職場で自分の能力を伝えられる
- 必要な配慮を具体的に説明できる
- 周囲とのコミュニケーションがスムーズになる
説明する力がついてくると、誤解やすれ違いも起きにくくなり、他者と安心して働ける関係性が作れます。
結果的として自分らしい働き方や、仕事の選択肢を広げることにもつながります。
転職活動で判断に自信が持てる
自己分析が進んでいると転職活動の中で迷いにくくなり、判断に自信が持てるようになります。
転職活動では「どんな職場を選ぶか」「この求人に応募するかどうか」など、たくさんの意思決定が必要です。
自己分析で方針が決まっていれば、決断のたびにかかる負担は少なくなります。
- 志望する企業や求人が明確になる
- 応募や辞退の判断がしやすくなる
- 内定後の意思決定にブレが出にくい
自己分析が浅いままだと、「この求人で本当にいいのかな」「何を優先したいのか分からない」と迷いやすく、応募前や内定が出たあとにモヤモヤするケースは多いです。
自己分析を通じて自分の優先順位や「軸」が定まっていれば、納得感のある判断がしやすくなります。結果として、満足度の高い転職にもつながるでしょう。
キャリアアップに向けた動き方が見えてくる
自己分析は目の前の仕事のためだけでなく、3年後・5年後を見据えたキャリアアップの道筋を整理するうえでも役立ちます。
私たちの中には「スキルに自信がない」「将来のイメージを持ちにくい」といった、長期視点が苦手な人は多いです。
自己分析を通じてスタート(現状)とゴール(目指す方向)が決まれば、今やるべき行動も具体的になります。
- 自分の伸ばしやすい分野が見えてくる
- 将来に向けたスキルアップの方向性が決まる
- 次に何をするか(資格・情報収集など)が明確になる
やみくもに動くのではなく、自分にとってのキャリアアップの指針を作れるのは大きなメリットです。
自己分析は「行動する」までがセット


自己分析で方針が決まったら、具体的な「行動」に移すところまでがセット。分析しただけで終わらせず、改善やステップアップに進めていきましょう。
代表的な選択肢を3つ紹介します。下記以外も含め、自分にあった「次の一歩」を見つけてみてください。



分析しただけで終わらせないことが大事!
スキルアップに取り組む
自分に足りないスキルや、更に伸ばしたい能力が見つかった場合は、具体的なスキルアップに取り組みましょう。
現職での評価を上げたり、将来の可能性を広げたりと、未来を見越した「自己投資」になります。
手当たり次第に飛びつかず、目的をもってスキルアップにチャレンジしてください。
- 強みに関連する資格を取得する
- 弱みや特性の対処法を書籍で学ぶ
- 効率化のためのツールを触ってみる
スキルアップは試験に合格して手に入れられる資格だけでなく、「自分ならできる」という自己効力感も高めます。
自己効力感とは、目標を達成するための能力を自らが持っていると認識することを指します。
引用:GLOBIS
簡単にいえば、「自分ならできる」「きっとうまくいく」と思える認知状態のことです。
「やればできる」という感覚は、気持ちがネガティブに傾きやすい人ほど重要。小さくても成功体験を積むことで、気持ちが折れにくくなります。
スキルアップの意欲は思い立った直後が一番高く、どんどん熱が冷めていきます。学びたいと思ったときに、具体的な行動へ結び付けましょう。
詳しくは、「発達障害者の仕事に役立つオススメ資格まとめ」の記事をお読みください。
転職活動を具体的に進める
現状を冷静に分析して「転職した方がいい」と判断した場合は、迷わず行動に移しましょう。
具体的には、以下の作業が必要になります。
- 転職エージェントに登録して実際の求人を知る
- 絶対に譲れない転職の軸を決める
- 応募書類のベースを完成させる
①「転職エージェント」を使って求人情報を集めながら、②「転職の軸」で応募する求人の方針を固めましょう。①と②はセットで進めていくと効率的です。
方針が決まったら③「応募書類のベース」を作り、効率的に応募が進められる状態を整えてください。
「発達障害がある人の転職活動の進め方」の記事を参考にしつつ、着実に転職活動を進めましょう。
現状維持で「待ち」に徹する
自己分析をした結果、「今は動かない」という結論になることも十分あり得ます。
- 今の環境は自分に合っている
- 職場よりも優先することが見つかった
- あと半年待ったら再検討する
客観的に自分の状況を見つめ直し、むやみに動く必要がなければ「保留」も選択肢の一つ。現職で経験を積み、勤続年数を増やすことで得られる信頼もあります。
たとえば就労定着支援の期間(最大3年間)は焦らず定着に取り組む、来年の昇給・昇格がなかったら再検討する、といった自分なりの目途を立てておくと良いでしょう。常に不安を抱えるよりも、期間を決めて「待ち」に徹する方が精神的に余裕を持てます。
「待ち」の判断をした場合でも、定期的な自己分析や、応募書類の更新は継続しましょう。半年や一年に一度、区切りの良いときに現状分析をするのは大切です。
場合によっては、職場環境が急に変わることもあります。状況の変化に合わせて、いつでも行動に移せるよう準備しておきましょう。
まとめ|発達障害者こそ自己分析で「見える化」しよう
本記事では、発達障害のある方が「自分に合った働き方」を見つけるための、自己分析の進め方を紹介しました。
- 自己分析は、現状と目指す方向を言葉にする作業
- 得意・不得意を整理し、働きやすい環境を考える
- キャリアアップや転職活動にも役立つ判断材料になる
自己分析は一度やったら終わりではありません。定期的に振り返りながら、今の自分に合った方針をアップデートしていきましょう。
まずは思い出しやすい事実を書き出すことから始めてOKです。少しずつ手を動かして、自分にとって納得のできる方針を考えてみてください。



ちょっとずつ進めるだけでも効果あり!
\オススメアプリ!/
自己分析にオススメしたいツールはミイダス。誰でも無料で利用でき、ストレス要因・職務適性・上下関係適性などさまざまな回答結果を得られます。
特にストレス要因は発達障害を持つ方が働くうえで意識すべきポイントのひとつ。どんなときに負荷がかかるのかを知っておくだけでも、職場定着や活躍にいい影響を与えるでしょう。