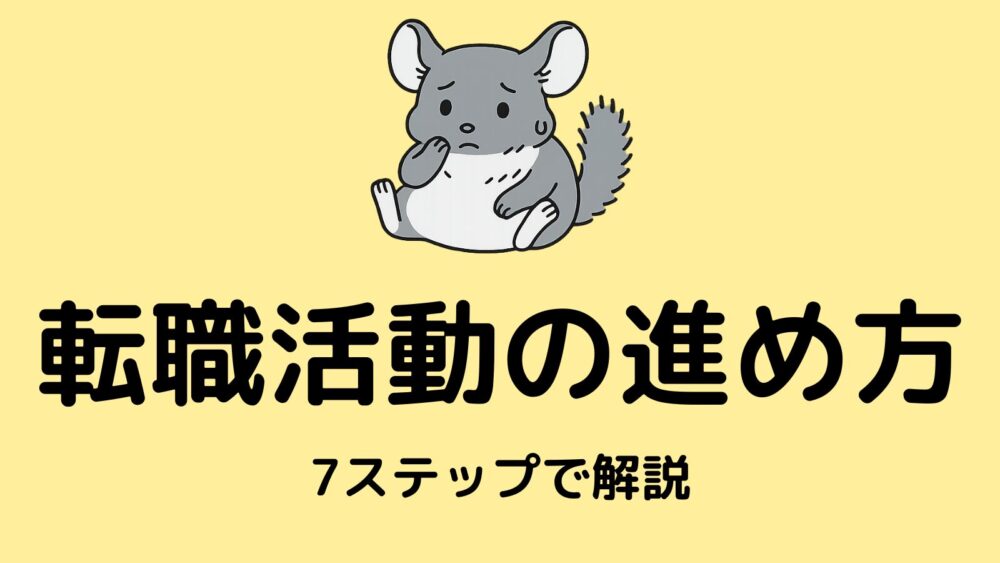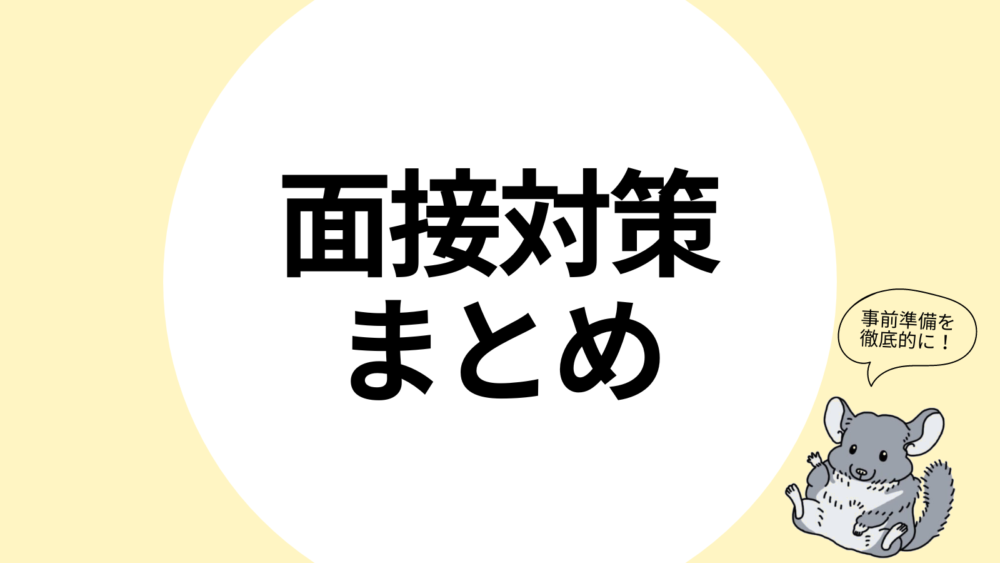- 面接でうまく話す自信がない…
- 予想外の質問がきたらどうしよう!
- 本番までに何をすればいいの?
書類選考を通過したら、採用担当者と直接話す面接が行われます。
発達障害がある人にとって面接は、ただでさえ緊張しやすい場面。伝えたいことがまとまらなかったり、想定外の質問にうまく返せなかったりと、苦戦する人は多いです。
だからこそ面接で失敗しやすいポイントや、事前にできる準備を知ることで、不安を大きく減らすことが可能です。
 よしだ
よしだ私も緊張しすぎて喋れなかった経験があるよ。




本記事では、面接前の準備~当日の流れ、面接後の振り返りまでを具体的に解説しています。クローズ就労で働く人や、診断がないグレーゾーンの方でも使えるようにまとめました。
面接に不安を感じている方や、これから選考に進む方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
発達障害がある人の面接対策のポイント
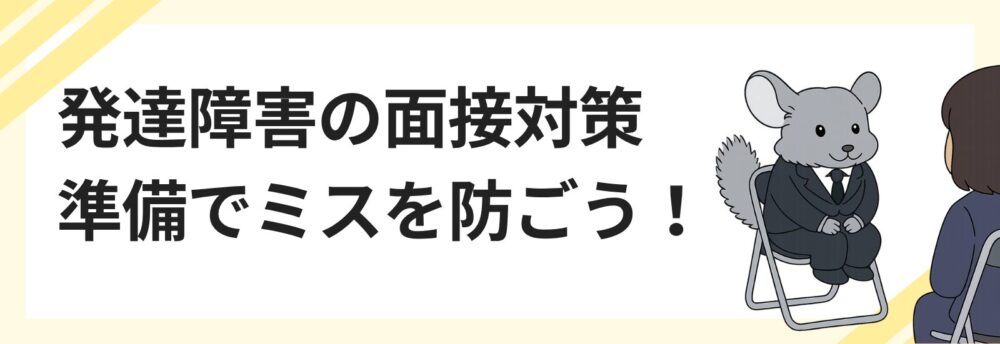
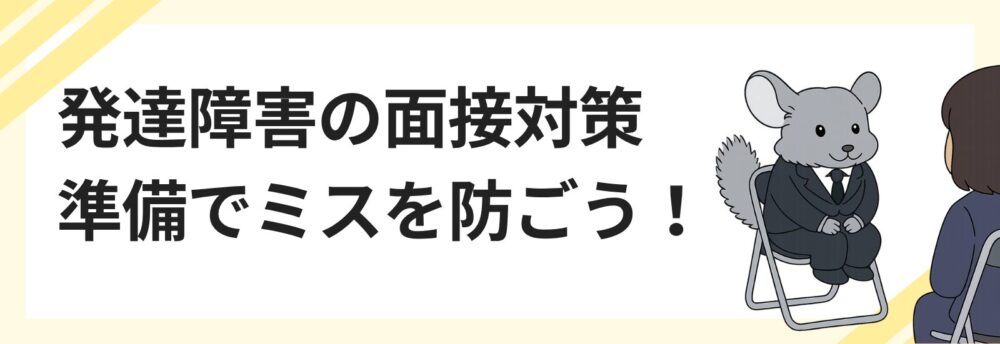
面接は、発達障害の特性がある人にとってつまずきやすい場面の一つです。特性や苦手意識によって、うまく対応できない場合もあるでしょう。
- 話す順番を整理しにくい
- 質問の意図がうまくつかめない
- 緊張で言葉が出てこない
準備なしで面接に臨んでしまうと、自分の良さを伝えきれず後悔する可能性もあります。
だからこそ、特性に合わせた面接対策を事前に行うことがとても重要です。



ぶっつけ本番じゃ、受かるものも受からない!
特性に合った事前準備の大切さ
面接では、その場で質問に答える力や、空気を読んだやり取りが求められることがあります。
発達障害がある人のなかには、「予測しにくい場面」が負担になりやすく、うまく伝えられない原因になることも少なくありません。
難しいからこそ事前に、自分の特性に合った準備をしておくことが非常に大切になります。
たとえば、聞かれそうな質問と答えをあらかじめメモにまとめておくのも対策のひとつ。そのメモを実際に声に出してみることで、「どこで詰まりやすいか」「どう伝えれば自然か」を掴めます。
事前に準備しておけば、当日の緊張が軽くなり、自信を持って臨みやすくなるでしょう。
具体的な準備方法や当日の流れは、以下の章で詳しく解説しています。
グレーゾーンの人も特性への対策は必要
発達障害の傾向はあっても診断に至らず、手帳がない「グレーゾーン」の人も、自分の特性に合わせた対策が必要です。
- 会話のテンポが速くてついていけない
- 質問の意図がつかめず焦ってしまう
- 話す順番を整理するのに時間がかかる
苦手な場面を想定し「どう乗り切るか」を考えておくだけでも、本番での安心感は違ってきます。
紹介する対策の中に、自分に合いそうな工夫があれば、ぜひ取り入れてみてください。
オープン・クローズ就労による面接対策の違い


面接対策は、働き方によっても少し変わってきます。障害の開示・非開示に合わせて、伝え方や準備のポイントを整理しましょう。
オープン就労では面接の中で、障害のことや配慮してほしい点を自分の言葉で伝える場面があります。
企業側がどこまで理解しているかはケースバイケースなので、「どんな配慮があれば働きやすいか」「実際にどんな工夫をしているか」を具体的に話せるようにしておくのが大切です。
一方でクローズ就労では、特性に触れずにやりとりする必要があります。
あえて言葉を選んだり、自分の工夫を自然な形で伝えたりする場面もあるでしょう。「説明しすぎずに、自分らしさをどう伝えるか」がポイントになります。
どちらが正しい・間違っているということはありません。自分に合った働き方や、職場との相性を考えたうえで、方針に合わせた面接対策をしていくことが重要です。
面接本番に向けた準備


面接で自分の魅力を伝えるには、「どんな質問が来るか」「どう話せば伝わるか」を整理しておく必要があります。
発達障害のある人にとって、会話のテンポや言葉選びに不安を感じる場面もあるかもしれません。だからこそ、本番を想定した準備をしておくことで、自信をもって話せる可能性がぐっと高まります。
この章では、面接当日までにやっておきたい具体的な対策を紹介します。
- 企業研究と求人情報の再確認
- 面接で聞かれやすい質問と回答の準備
- 模擬面接による練習
- 面接当日の準備



準備や対策は裏切らない!
自己分析と企業研究の再確認
面接前には、応募先の企業情報や自分自身の志望理由などのデータを、あらためて見直すことが大切です。
自己分析では、特性や働き方の希望、転職理由などを整理しておきましょう。
- 何が得意で何が苦手なのか
- どんな働き方をしたいのか
- 転職において譲れない条件は何か
面接では、仕事に対する考え方や価値観などを深掘りされることがあります。
企業研究では、応募先の企業に対してどんな印象を持ったか振り返ってください。
- どんな事業をしているか
- なぜこのポジションを募集しているのか
- どんな人物像を求めているか
応募書類のコピーを見返しながら、「この会社では何を伝えるべきか」を改めて整理しておくと安心です。
面接で聞かれやすい質問と回答の準備
面接では、「この質問はほぼ確実に聞かれる」と言ってもいいほどよく出る、定番の項目があります。
あらかじめ質問と答えを整理しておくことで、自信を持って話しやすくなるでしょう。
さらに、想定外の質問に備える「深掘り対策」や、面接の最後に聞かれる「逆質問」も事前に用意しておくと安心です。



書き出して声に出す。それだけで本番の安心感が全然違う!
面接でよく聞かれる質問リストを作る
発達障害がある人にとって面接は、ただでさえ緊張や不安を感じやすい場面。
あらかじめ聞かれやすい質問と回答のリストを作っておくことで、面接本番への不安が軽くなります。
具体的には、以下の項目を中心に考えていきましょう。
- あなた自身に関すること
- 過去の経験に関すること
- キャリアに関すること
- 発達障害に関すること
- メンタル面に関すること
企業や面接官によって細かな違いはありますが、定番の質問はある程度パターン化されています。
履歴書や職務経歴書と照らし合わせながら、「自分が面接官だったら、どこを聞くか?」という視点で考えてみましょう。
面接本番では、文章ではなく声に出して面接官へ伝えます。リストを作ったら、実際に声に出して読み上げてみてください。
話してみると文章の違和感に気づきやすく、回答の精度も上がります。
発達障害がある人の面接で質問されやすい項目は、以下の記事で詳しく説明しています。
深掘り質問にも備えておく
面接では、表面的な質問に答えるだけでなく、「深掘り質問」をされることがよくあります。
たとえば「あなたの強みは何ですか?」と聞かれたあと、「なぜそう思うのか?」「実際にその強みを発揮した場面は?」といった追加の質問が来るイメージです。
深掘り質問とは、書類だけでは分からないあなたの資質や行動を詳しく知るための質問のこと。発達障害がある人に限らず、一般の転職シーンでも多く取り入れられています。
準備をしておかないと、回答に詰まりやすくなります。結果として「この人は本当のところをまだ分かっていないのかも」と判断されてしまう可能性があるでしょう。
特に発達障害がある人の場合、「自分のことを言葉で説明するのが苦手」「考えていることを整理しづらい」といった特性から、深掘り質問に弱い人が多いです。
回答を作るときは、「What(何を)」「Why(なぜ)」「How(どうやって)」の3つを意識してみてください。
- What:どんな経験・出来事だったか
- Why:そのとき、どう考えたか/なぜそうしたのか
- How:どんな工夫や行動を取ったのか
この3つを整理しておくことで、どんな質問にも冷静に答えやすくなります。
準備して終わりではなく、「なぜそう思った?」「どうしてそうした?」と自分にツッコミを入れながら、何度か深掘りしておくのが効果的です。
逆質問をあらかじめ用意しておく
面接の最後に聞かれる「何か質問はありますか?」という逆質問は、実はとても大切な場面。
発達障害がある人にとっては、自分に合った働き方ができるかどうかを見極める貴重なチャンスでもあります。
面接官の雰囲気や、配属予定の部署について質問することで、職場の温度感や配慮体制を把握しやすくなります。
逆質問を通じて入社意欲をアピールしたり、自分の考えや姿勢を補足したりもできるでしょう。
とはいえ、面接の最後は緊張もピークになりがち。聞きたいことがあっても、頭が真っ白になってしまうことはよくあります。
そんなときに備えて、事前に3つ以上の質問をメモしておくと安心です。
実際にその場で手帳を開き、「質問を用意してきたので、見ながらでもよろしいでしょうか」と丁寧に伝えれば問題ありません。
さらに、面接の途中で疑問が解消された場合は、無理に質問をひねり出す必要はありません。以下のように伝えるだけでも、十分に好印象を残すことができます。
例:「○○について質問しようと思っていましたが、ご説明のおかげで解消されました。ありがとうございました。」
逆質問は「自分が企業を見極める時間」でもあります。
質問する内容をしっかり準備しておくことで、働きやすい職場かどうかを判断するヒントが得られるはずです。
逆質問の考え方や具体例については、以下の記事で紹介しています。合わせてお読みください。
模擬面接による練習
「面接になると頭が真っ白になってしまう」「言いたいことをうまく言葉にできない」と感じる人は、模擬面接での事前練習が効果的です。
模擬面接とは、支援者や転職エージェントに面接官役をお願いし、本番同様の形式でやり取りを行う面接練習のこと。
質問への回答力だけでなく、雰囲気に慣れることで緊張をやわらげる効果もあります。
発達障害がある人のなかには、「予想外の質問に弱い」「沈黙が怖くて早口になる」など、自覚しにくいクセが出やすい場合もあります。
模擬面接を通して振り返りを行うことで、苦手な場面を事前に把握し、改善につなげられるでしょう。
また模擬面接では、以下のような準備をしておくと、より効果的に取り組めます。
- どんな質問に対して不安があるか、あらかじめ洗い出しておく
- 録画機能を使って、自分の受け答えを客観的に振り返る
- 面接官役の人にフィードバックをもらい、改善点を明確にする
練習のうちに失敗することで、本番での成功率が高まります。「まだ準備不足かも…」と感じる人ほど、積極的に活用してみてください。
面接当日の準備
面接当日は緊張や不安により、いつも通りの行動が難しくなることもあります。
当日にやるべきことは最小限にして、「面接会場へ向かうだけ」の状態まで準備を済ませておくことが大切です。
- 服装
- 持ち物
- 移動手段
この3つを前日までに整えておくことで、当日の緊張をぐっと減らせます。冷静に面接を受けるためにも、事前準備は早めに済ませておきましょう。
① 服装の確認
面接では第一印象がとても重要です。迷ったときは、スーツが最も無難な選択。黒・紺・グレーなどの定番色を選び、白シャツやブラウスと合わせて清潔感を意識しましょう。
靴は革靴が基本。前日までに磨いておくと安心です。手持ちの服で迷う場合は、安価なもので良いので一着スーツを用意することをオススメします。
② 持ち物の準備
当日の忘れ物を防ぐため、以下の持ち物をリストアップしておきましょう。
- 履歴書・職務経歴書のコピー
- 筆記用具・メモ帳
- 面接先の住所・連絡先・面接日時を書いたメモ
- スマートフォン(充電済)、またはモバイルバッテリー
面接では応募書類の内容から質問されることも多いため、コピーを手元に置いておくと直前の見直しに役立ちます。
③ 移動手段とルートの確認
面接当日に慌てないよう、会場までの移動ルートと所要時間を事前に確認しておきましょう。
- 電車やバスは、遅延や乗り換え時間を考慮して早めに出発
- 車移動の場合は駐車場の有無と周辺のコインパーキングをチェック
- 可能であれば事前に下見しておくと安心
天候や交通状況にも左右されるため、「当日は○分前には現地に着く」といった逆算ができると、落ち着いて行動できます。


発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?
- 自己分析が進まない → 自分の強みが分からない
- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない
- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配
こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼りましょう!
- 書類添削+面接対策で合格率UP
- 特性に合う求人を一緒に選べる
- 日程調整や企業とのやりとりを代行
もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?



方向性の相談だけでもOK。初めてなら「dodaチャレンジ」がオススメだよ!
\ 発達障害の当事者が厳選! /
面接当日の流れと注意点


面接当日は、事前の準備がいかに整っているかが結果を左右します。
スケジュールに余裕がなかったり、思わぬトラブルに動揺してしまうと、本来の力を発揮できないまま面接が終わってしまうこともあるでしょう。
面接本番では、以下の流れで進みます。想定外の場面にも対応できるよう、事前に流れを把握しておくことが大切です。
面接会場に着いたら、まず受付で担当者に面接に来たことを伝えましょう。企業によっては別室に案内される場合もあるので、指示に従ってください。
面接官に呼ばれたら、ノックをしてから入室してください。入室後は「本日はよろしくお願いいたします」と挨拶を伝え、面接官の指示に従って着席します。
面接官からご自身のことについて、いくつかの質問を受けます。事前に想定される質問への回答を考えておくと、落ち着いて答えられるでしょう。
面接官からの質問がひと通り終わると、「何か質問はありますか?」と尋ねられることがあります。この機会に仕事内容や職場の環境などの質問を行い、疑問点を解消しておきましょう。
面接が終了したら面接官に感謝を伝え、「本日はありがとうございました」と挨拶をして退室します。退室時も丁寧な態度を心がけましょう。



面接の後は情報を整理する時間も確保しよう!
面接で普段通りの実力を出すため、「何を意識するか」について紹介します。
- 当日のスケジュール
- 面接を受けるポイント
- 面接で困ったときの対処法
当日のスケジュール
面接当日は、なるべく余裕を持ったスケジュールで行動することが大切です。
時間に追われてバタバタしてしまうと、緊張がさらに高まり、面接本番にも悪影響が出てしまいます。
スケジュールの余白は「気持ちの安定」につながり、本来の自分を出しやすくなるでしょう。
以下のポイントを押さえ、万全の状態で面接に臨んでください。
- 忘れ物がないか出発前に再確認
- 面接会場には早めに到着
- 面接前後は予定を入れずに集中
忘れ物がないか出発前に再確認
面接当日の朝は、予想以上に慌ただしくなりがち。焦って家を出たあとに「アレを忘れた!」と気づいても、取りに戻る余裕はないかもしれません。
前日までに必要な持ち物をすべてそろえ、出発時はカバンを持っていくだけにしておくのがオススメです。
たとえば、以下のようなものは最低限そろえておきましょう。
- 履歴書・職務経歴書のコピー
- 筆記用具・メモ帳
- 面接先の住所・連絡先・日時を記載したメモ
スマホに情報を入れている場合は、充電残量の確認やモバイルバッテリーの持参も忘れずに。準備不足によるミスを防ぐためにも、「面接の持ち物チェック」は前日夜までに行いましょう。



移動してから忘れ物に気づくともう遅い!事前準備が大切だよ。
面接会場には早めに到着
遅刻が心配な人は、予定時刻の30分~1時間前に現地に到着しておくと安心です。
ギリギリの到着を目指すと、次のようなトラブルで遅刻してしまう可能性があります。
- 公共交通機関の遅延
- 道路の渋滞
- 急な体調不良
面接は仕事と同じく、遅刻厳禁です。「時間を守れるか」によって、大きく減点される場合もあるでしょう。
到着後すぐに建物へ入る必要はありません。近くのカフェや公園で一息つき、身だしなみや持ち物の最終確認をする時間にあてると気持ちにも余裕が生まれます。
カツカツのスケジュールで面接に臨むのではなく、「丁寧に臨むための準備時間」を作って余裕のある行動を意識しましょう。
面接前後は予定を入れずに集中
面接当日は、前後のスケジュールに余白を持たせましょう。
面接直前に予定を入れると、時間が押したり移動がギリギリになったりするリスクがあります。たとえ予定時間に間に合ったとしても、面接に集中できなくなる可能性が高いです。
例えば「1時間で終わるだろう」と考えて面接前に予定を詰めてしまうと、予想より長引いた場合に焦ってしまい、面接そのものの集中力が切れてしまうこともあります。
面接は、たった一回の受け答えが合否を左右する大切な場面。時間に追われることで、本来の実力を出し切れずに終わってしまうのは非常にもったいないことです。
最低でも、面接の前後に1時間は余白を残すことをおすすめします。スケジュールにゆとりがあるだけで、心の余裕も大きく変わってくるでしょう。



面接は遅刻厳禁!前後も空けて余裕のある日程調整をしよう。
面接を受けるポイント
面接では、回答内容だけでなく立ち振る舞いや伝え方など、全体的な印象が評価につながります。一方的に喋る場ではなく、企業との対話を通じて「お互いを理解する場」と捉えましょう。
以下の3つの視点から、過去の面接を振り返りながら対策を立てておくと安心です。
- 面接官へ与える印象
- コミュニケーションの取り方
- 質問への適切な回答



「どう伝えるか?」もめっちゃ大事!
面接官へ与える印象
面接において、第一印象はとくに重要。第一印象がその人のイメージとして残る「初頭効果(しょとうこうか)」というものがあります。
初頭効果とは、初めての出会いや初めて知った言葉など、当初の刺激が、人間の印象形成に強い影響を与える心理効果です。
引用:聖泉大学
入室してから「よろしくお願いします」と挨拶するまでの数秒間で、どんな印象を持たれるかが決まってしまいます。
このタイミングでつまずくと、その後の面接でリカバリーに余計な時間やエネルギーを取られてしまうため、特に注意が必要です。
些細なことで面接を無駄にしないためにも、「最初の3秒」で良い印象をつかみましょう。
- 服装と身だしなみ
- 表情や姿勢
- 声の大きさ・抑揚
コミュニケーションの取り方
面接は、ただ自分の情報を一方的に伝える場ではありません。企業側とお互いに理解を深める「双方向のやりとり」が求められます。
このときに大切なのが、「何を伝えるか」だけでなく「どう伝えるか」。伝え方の印象が、評価に大きく影響する場面も少なくありません。
表情や視線など見た目や仕草による「視覚情報(Visual)」が人に与える影響度は55%、
声の大きさや話すスピードなどの「聴覚情報(Vocal)」は38%
会話そのものの内容である「言語情報(Verbal)」は7%
引用:パーソルグループ
つまり、相手に伝わる印象のうち 93%が「非言語」。言葉の中身よりも、見た目・声・話し方といった「伝え方」が評価に影響しやすいです。
印象で損しないためにも、以下のポイントを意識してみてください。
- ゆっくり、はっきりとした口調で話す
- 回答は結論を先に伝え、主張を理解してもらう
- 相づちを打ち、話を理解している姿勢を示す
とくに「ゆっくり、はっきり」は重要です。緊張すると早口になりやすいため、一文ごとに区切るような意識で話すと余裕を持ちやすくなります。
質問に答えるときは、「何が言いたいのか」が伝わるように、まず結論を伝えましょう。そのあとに理由や具体例を添えるとスムーズです。
面接官の質問や話には、しっかり相づちを打つのもポイント。視覚的に「話を聞いていますよ」という姿勢を見せることで、信頼感も高まります。
面接は一方通行ではありません。「伝えたつもり」で終わらず、相手に伝わっているかを意識することで、会話の質がグッと上がります。
質問への適切な回答
面接では、ただ質問に答えればいいというわけではありません。質問の意図を正しく理解し、的確に答えることが求められます。
表面的な質問でも、深堀りされるケースは多いもの。準備不足のままだと、思わぬ質問で焦ってしまい、本来伝えたいことが伝えられなくなるかもしれません。
万が一、質問の意図が読み取れなかったときは、無理に答えようとせず「こういう意味で合っていますか?」と確認を取るのがオススメ。
質問には一問一答で終わらず、理由や具体例を添えることも有効。
例えば、「優先順位を意識しています。」とだけ答えるのではなく、以下のように具体例をセットで伝えましょう。
ただ端的に回答するよりも、面接官に理解されやすくなります。
面接の基本的な流れは、面接官の質問に対して回答する形で進みます。何を聞かれるかは企業や面接官次第ですが、多くは応募書類に書いた内容について質問されることが多いです。
- 志望動機
- 職務経歴
- 強みや弱み
- 障害特性
面接当日にぶっつけ本番で対応せず、事前に回答を考えたり、模擬面接を実施したりして対策しましょう。
面接で困ったときの対処法
面接では、想定外の質問や進行に戸惑い、頭が真っ白になることもあります。
発達障害のある方の中には、突発的な変化やプレッシャーに弱い傾向がある方も多く、事前準備だけでは対処しきれない場面もあるでしょう。
ここでは、特に多い2つの困りごとと、その対処法を紹介します。
- 緊張・パニックになったとき
- 質問の意図がわからないとき
緊張・パニックになったとき
発達障害がある方にとって、面接のような非日常な場面は、緊張や感覚の過敏さからパニック状態に陥りやすいことがあります。
特に、「静かに話さなきゃ」「うまく答えなきゃ」と意識しすぎると、頭が真っ白になってしまうケースも少なくありません。
重要なのは緊張そのものをなくすことではなく、緊張しすぎてパニックにならない工夫です。
自分が緊張していると気付いたら、以下の3つを試してみてください。
- 姿勢を正して深呼吸する
- 意識してゆっくり話す
- 「緊張している」と面接官に伝える
①姿勢を正して深呼吸する
緊張に気付いたタイミングで、まずは改めて姿勢を正して大きく深呼吸しましょう。緊張状態では呼吸が浅くなるため、呼吸を整えるのが難しくなります。
ポイントは一旦息をすべて吐き出し、その後に大きく息を吸うこと。肺の酸素がなくなることで、大きく息を吸うことが可能です。
ドキドキしたら、意図的にしっかり吸ってしっかり吐くことで自律神経などに働きかけ「感情をある程度コントロールできる」(本間教授)。
引用:日本経済新聞
②意識してゆっくり話す
緊張すると早口になってしまうときは、「、」「。」のタイミングを意識しておくと効果的です。句読点が、言葉の「ブレーキ」のような役割を果たしてくれます。
勢いで話し続けてしまうと、ペースがコントロールしづらくなります。「ここで一旦止まる」と決めておくことで、落ち着いた話し方がしやすくなるでしょう。
例)
- ×:前職ではデータ入力を担当していました。正確さを重視し日々の業務に取り組んでいました。
- 〇:前職では、データ入力を、担当していました。正確さを重視し、日々の業務に、取り組んでいました。
句読点があることで、聞き手にも伝わりやすく、自分自身も焦らず話せるようになります。
伝えたいという思いが強すぎたり、緊張したりしすぎても早口になりがちです。これって、少し自分を見失っている状態のときですね。
引用:ダイヤモンド・オンライン
③「緊張している」と面接官に伝える
どうしても緊張が強いときは、思い切って面接官に伝えるのも一つの手。「実はかなり緊張しています」と言葉にして伝えるだけで、案外すっきりして落ち着けます。
緊張しながら無理に面接を進めるよりも、一旦気持ちを落ち着かせてからリカバリーした方が効果的な場面もあるでしょう。
「自分は緊張している」ということを相手に伝えてしまう方法です。「緊張しているので、もし声が聞き取りにくかったら言ってくださいね」などと自分の状態を言葉にして相手に伝えると、「いま緊張していること」が共通認識となり、必死に隠す必要がなくなります。
隠すことへの意識から解放されると、落ち着きも取り戻しやすくなります。
引用:全薬グループ
過去に展示会のプレゼンリハーサルを見る機会があり、司会役の人が「実は私、結構緊張しています」と台本に入れているのを見かけました。
面接で毎回「緊張している」と言うのは少し違うかもしれませんが、万が一のときは使ってみてください。



誰だって面接は緊張するよ!緊張そのものよりも、リカバリー方法を身に付けよう。
緊張そのものは、真剣に面接と向き合っている証拠。しかし緊張をリカバリーする方法がないと、仕事でもトラブル時に冷静さを取り戻せない人と思われる可能性もあります。
面接本番でマイナスイメージを持たれないために、模擬面接を使ってうまく緊張と向き合いましょう。
緊張を一人で乗り越えられるスキルは、面接だけでなくその後の仕事にも役に立ちます。
質問の意図がわからないとき
面接では、抽象的な質問や、答え方に悩むような質問が出ることがあります。
事前に準備していなかった質問に戸惑い、うまく返せないと感じたときは、焦らず次のように対応しましょう。
- 質問と同じ言葉をオウム返しして時間稼ぎ
- 「予想外の質問でした」と伝える
- 回答が難しい場合は素直に伝える
質問と同じ言葉をオウム返しで返答し、考える時間を稼ぐことが有効です。例えば、以下のような回答を試してください。
面接官:あなたにとって「働く」とはなんですか?
求職者:私にとって「働く」とは、ですね……。「働くとは」~~です。
奇をてらった質問をし、反応を見るような面接官もいます。その場合は以下の対応がオススメです。
面接官:あなたを「色」で例えたら何色になりますか?
求職者:「色」…ですか。それは予想外の質問でした。少し考えさせてください。
どうしても返答が思いつかない場合は、素直に難しいことを伝えてしまうのも一つの手です。あわせて「質問の意図」を聞き返してみると、答えやすくなる可能性もあります。
「想定しておらずお答えが難しいです。申し訳ありません。~~のご質問ですが、その意図をお聞かせいただくことは可能でしょうか?」
予想外の質問は、思った以上にあります。困ったときでも冷静に対処できるよう、事前準備でさまざまな質問の回答を考えておくといいでしょう。
また自己分析をしっかり行い、自分のスキルや経験を整理しておくことも大切です。
突飛な質問を聞く面接官や、質問の意図が分からないケースなど、面接は「その場の対応スキル」が求められます。
模擬面接を何度か行い「場馴れ」することも、面接対策として有効です。



意図がわからなかったら、「聞き返す勇気」も大事!


発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?
- 自己分析が進まない → 自分の強みが分からない
- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない
- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配
こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼りましょう!
- 書類添削+面接対策で合格率UP
- 特性に合う求人を一緒に選べる
- 日程調整や企業とのやりとりを代行
もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?



方向性の相談だけでもOK。初めてなら「dodaチャレンジ」がオススメだよ!
\ 発達障害の当事者が厳選! /
面接後の振り返りと次への活かし方


面接を受けたら、必ず「振り返り」の時間を作ってください。
面接後は、次につなげるための重要な時間です。プレッシャーから解放されたくなる気持ちも分かりますが、以下の2つは忘れずに行いましょう。
- 面接内容をメモに残す
- フィードバックを受け取る



次の面接への準備も忘れずに!
面接内容をメモに残す
面接が終わった後はできるだけ早く、面接内容をメモに残しておきましょう。
- 採用担当の名前、役職などの基本情報
- 質問された内容と自分の回答
- うまく答えられなかった質問の内容
- 自分自身でうまくいったと思った点
聞かれた質問や回答内容、自分の印象や感じたことをまとめておけば、次回の選考や応募企業の比較を行うときに役立ちます。
- 次回以降の面接で同じ質問に迷わず答えられる
- 自分の受け答えをブラッシュアップできる
- 面接の印象を入社判断の材料にできる
面接の内容はすぐに記憶から薄れていきます。可能であれば面接の直後に、メモや振り返りの時間を確保しておきましょう。



面接の直後が一番、残せる情報が多い!
フィードバックを受け取る
転職エージェントを通じて応募した場合、面接後に企業からのフィードバックを受け取れることがあります。
- 応募者の印象
- スキルの過不足
- 社風とのマッチング
直接応募と違って、転職エージェント経由の面接では、選考通過・不採用に関わらずフィードバックがあるケースは多いです。
企業とエージェントがやり取りする中で、「どんな人が合うか」をすり合わせていく仕組みになっているためです。
- 選考通過:評価されたポイントを共有するフィードバック
- 不採用:今後のマッチング精度を高めるフィードバック
特に志望度の高い求人に対しては、エージェントから企業側へプッシュしてもらえる可能性もあります。面接が終わった後は、担当アドバイザーとコンタクトを取りましょう。
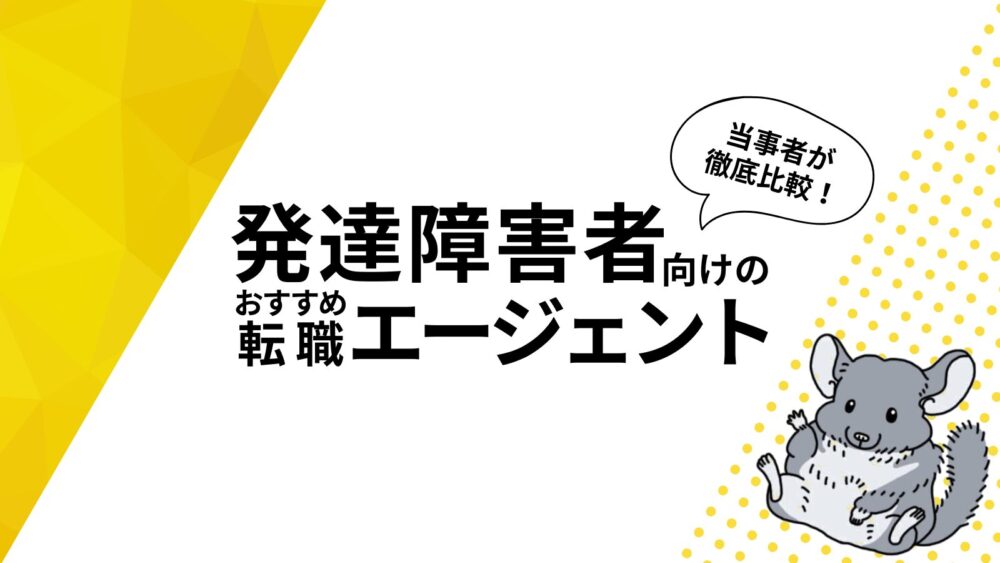
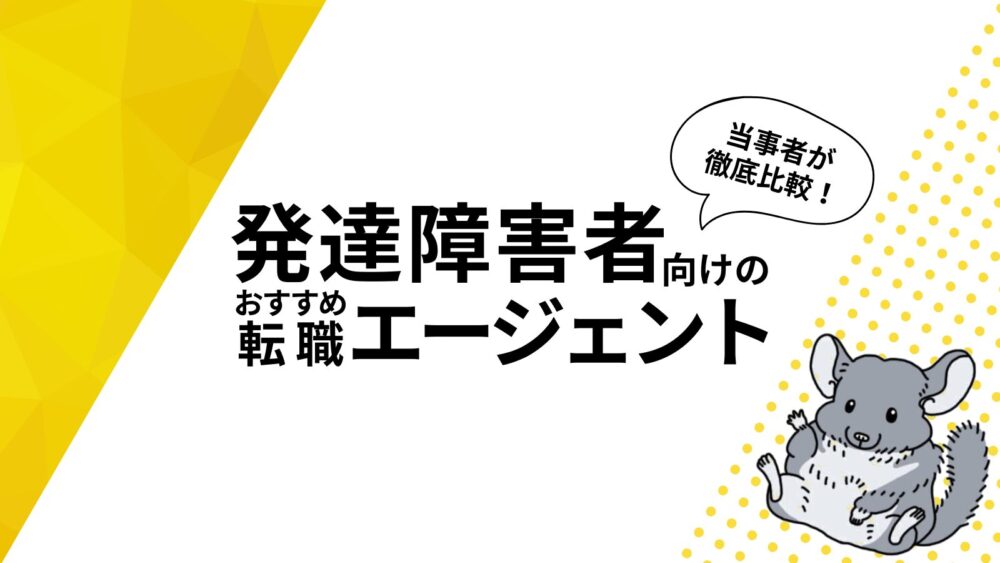
次回への準備
面接が終わったら、次の選考に向けた準備も始めておきましょう。
答えにくかった質問や、話していて違和感のあった部分は、早めに振り返っておくのがオススメです。
たとえば「志望動機がうまく伝わらなかった」「自己紹介の途中で言葉に詰まった」といった場面は、次の面接でも繰り返す可能性があります。
うまくいかなかった点だけでなく、「成功したと感じたこと」も整理しておくと、次回の自信にもつながるでしょう。
ちょっとした気付きや違和感をひとつずつ修正していくことで、自分なりのパターンができていきます。
改善できそうなポイントを見つけ、少しずつ調整してみてください。
面接が通らないときの対処法


面接がなかなか通らないと感じたときは、まず過去の面接内容を振り返ることから始めましょう。
- どんな質問をされたか
- どう答えたか(自分の伝え方・表現)
- どの部分を深掘りされたか
回答に添えたエピソードや、質問されたタイミングも含めて見直すことで、どこにズレがあったのか気づける場合があります。
面接官とのやり取りの中で、誤解や認識違いが起きていなかったかも振り返りましょう。
- 同じような質問を何度か聞かれた
- 深掘り質問で繰り返し確認された
- 面接官の表情や反応から納得していない印象を受けた
発達障害がある方にとっては、話し方や伝え方によって意図が正しく伝わらないケースも。企業側が配慮の難しさを感じた場合、不採用になる場合があります。
落ち込む気持ちが出てくるのは仕方がないことですが、「何が原因だったのか」「次に活かせることはあるか」と視点を変えてみることも大切です。
転職エージェントを利用している場合は、企業から転職エージェントへ「不採用の理由」を伝えていることが多いです。
次回に活かせるヒントが得られる可能性もあるため、気になる場合はアドバイザーに相談してみてください。



落ちたことよりも次につなげる方が大事!
一次面接と二次面接(最終面接)の違い
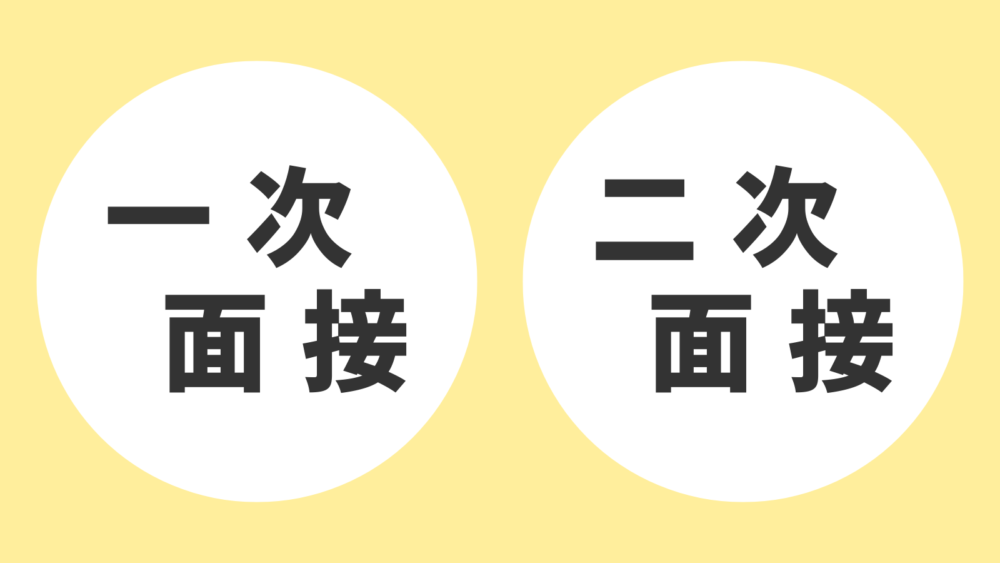
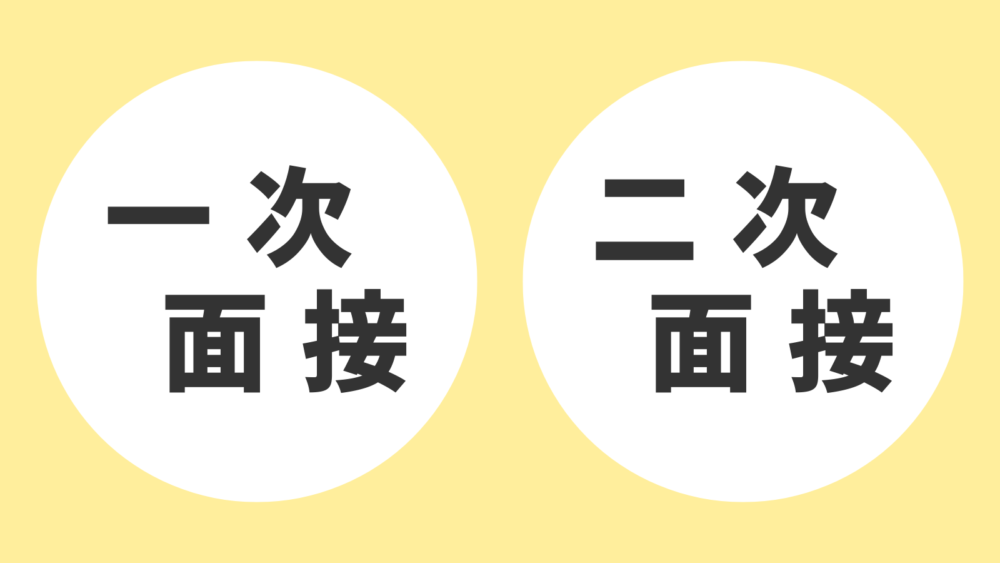
面接は通常、複数回に分けて実施されます。それぞれの回によって面接官や評価の観点が異なるため、事前に整理しておくことが大切です。
| 選考 | 一次面接 | 二次面接 |
|---|---|---|
| 面接官 | 人事担当者 現場担当 若手社員など | 人事責任者 部長クラス 社長・役員など |
| 注目 | 実務能力や業務とのマッチ度 ビジネスマナー・基本的な適性 | 仕事への価値観や将来的なポテンシャル 配慮の実現可能性や企業との相性を見られる |
一次面接では、業務適性や基本的なコミュニケーション力、障害特性に対する自己理解などが重視されます。ここで「一緒に働けそうか?」という視点での第一印象が評価されます。
二次面接(最終面接)では、会社全体の視点から「この人を採用するかどうか」を判断します。志望動機やキャリアプラン、配慮事項の現実性まで深掘りされることが多く、より本音に近い対話が求められます。
二次面接、最終面接と進んだ場合でも、不採用となる可能性は十分にあります。最後まで気を抜かず、誠実に対応しましょう。
選考の間に、実技試験や能力テストなどを実施する企業もあります。



一次面接は「能力と印象」、最終面接は「価値観や相性」を見られやすい!
オンライン面接の特徴とポイント


近年では、オンライン面接を実施する企業が多いです。
オンライン面接とは、直接企業へ訪問せず、ウェブ会議システムを使った面接方法。日程調整や会場確保がしやすく、オンライン面接を採用するケースは徐々に増えています。
オンライン面接は対面での面接と勝手が異なるため、特徴や注意点を押さえておきましょう。
- パソコンとインターネットが必須
- コミュニケーションが取りにくい
- カメラやマイクなどの環境で印象が変わる
オンライン面接の流れ自体は、通常の面接とほとんど変わりません。いきなりオンライン面接を受けるのが不安な方は、模擬面接をオンラインで実施するなどの対策をオススメします。



オンラインだからこその大変さもある!
面接対策には転職エージェントを使おう


面接対策に不安がある方は、転職エージェントのサポートを活用するのがオススメです。書類選考の通過後、どのように準備すればよいか迷ったときにも、具体的なアドバイスを受けられます。
転職エージェントを通じて応募すれば、企業の採用方針や募集背景など、求人票だけでは分からない情報を事前に知ることができます。
模擬面接を実施してもらえるケースも多く、回答の内容だけでなく話し方や印象面まで客観的にフィードバックしてもらえる点もメリットです。
そのほかにも以下のようなサポートが期待できます。
- 企業との面接日程調整の代行
- 面接後の企業からのフィードバック共有
- 次回面接に向けた改善アドバイス
障害を開示して働きたい方は、障害者を専門に扱う転職エージェントへ相談してみましょう。
障害者向けの転職エージェントには、さまざまな障害に専門性のあるアドバイザーが在籍。障害特性や事情に詳しい方も多いため、専門的なサポートが受けられます。
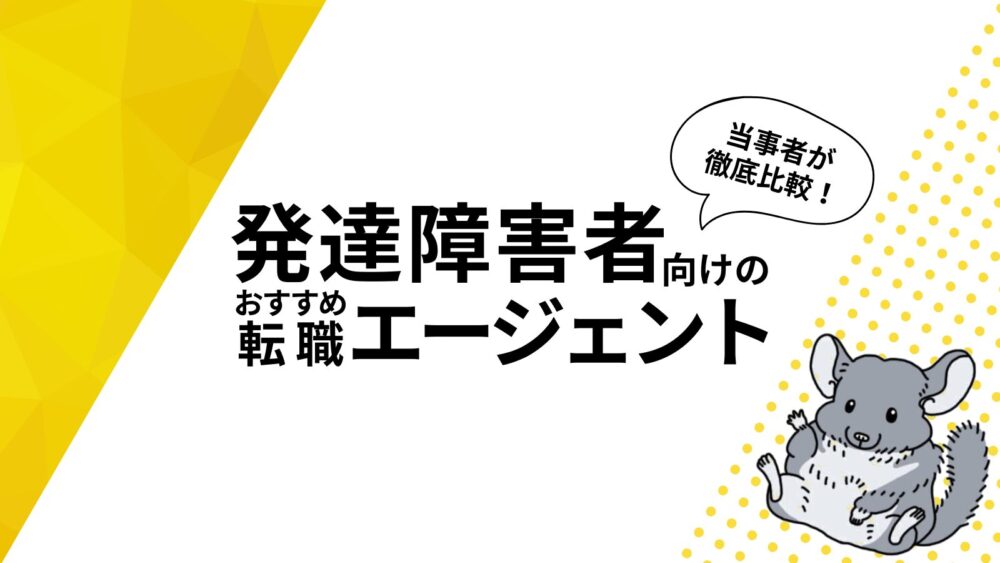
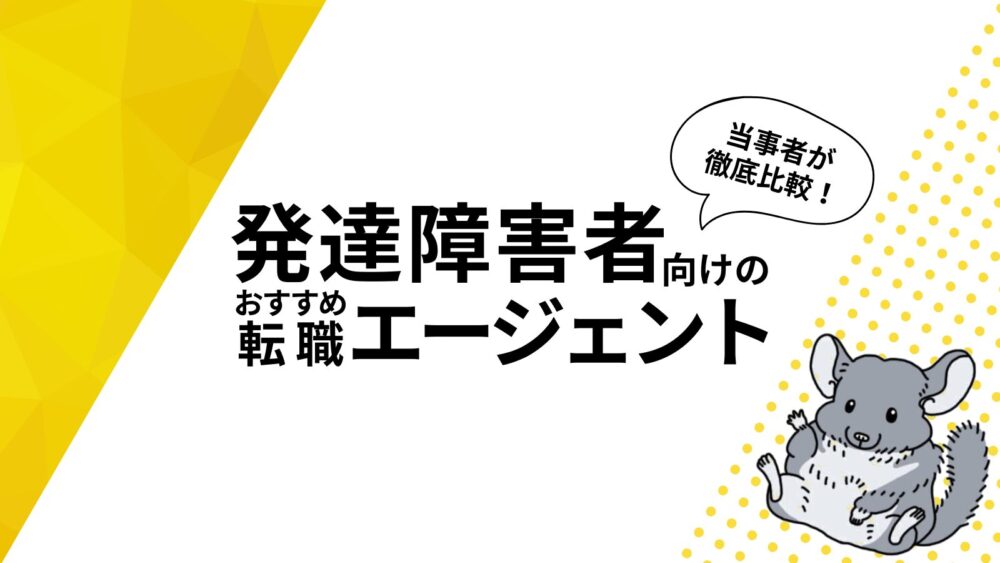
一方で、グレーゾーンの方やクローズ就労を希望する方の場合は、障害者向けエージェントの利用が難しいケースもあります。
その場合は一般転職向けの転職エージェントのなかから、相談しやすいアドバイザーと連携して面接対策を進めましょう。
面接対策のよくある質問


まとめ|内定を勝ち取るためには面接対策が重要
本記事では、発達障害がある方の面接対策について、一次面接・二次面接の違いや、面接前後にやるべき準備を紹介しました。
- 面接の段階ごとに評価されるポイントが異なる
- 障害特性と配慮事項は具体的に整理しておく
- 面接後の振り返りや、エージェント活用も重要
発達障害がある方にとって、面接は不安や緊張を伴いやすい場面ですが、事前準備や振り返りを重ねることで、少しずつ自信をつけていくことができます。
まずは、自分自身の特性を言葉にすることから始めましょう。伝え方を工夫すれば、あなたの強みが面接でもきちんと評価されます。
企業との相性を見極める機会でもある面接。納得できる転職のために、できる準備を一つずつ進めていきましょう。


発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?
- 自己分析が進まない → 自分の強みが分からない
- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない
- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配
こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼りましょう!
- 書類添削+面接対策で合格率UP
- 特性に合う求人を一緒に選べる
- 日程調整や企業とのやりとりを代行
もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?



方向性の相談だけでもOK。初めてなら「dodaチャレンジ」がオススメだよ!
\ 発達障害の当事者が厳選! /