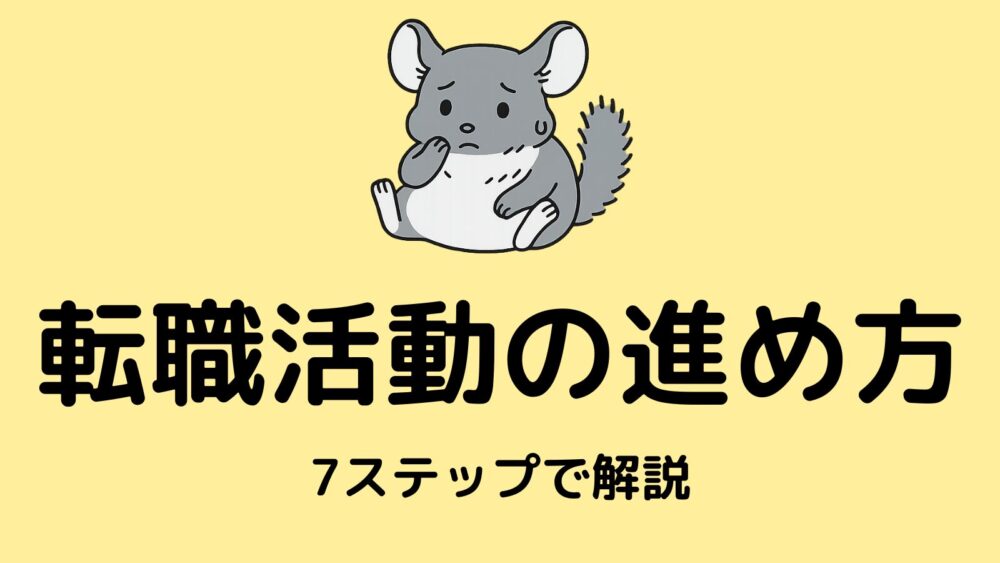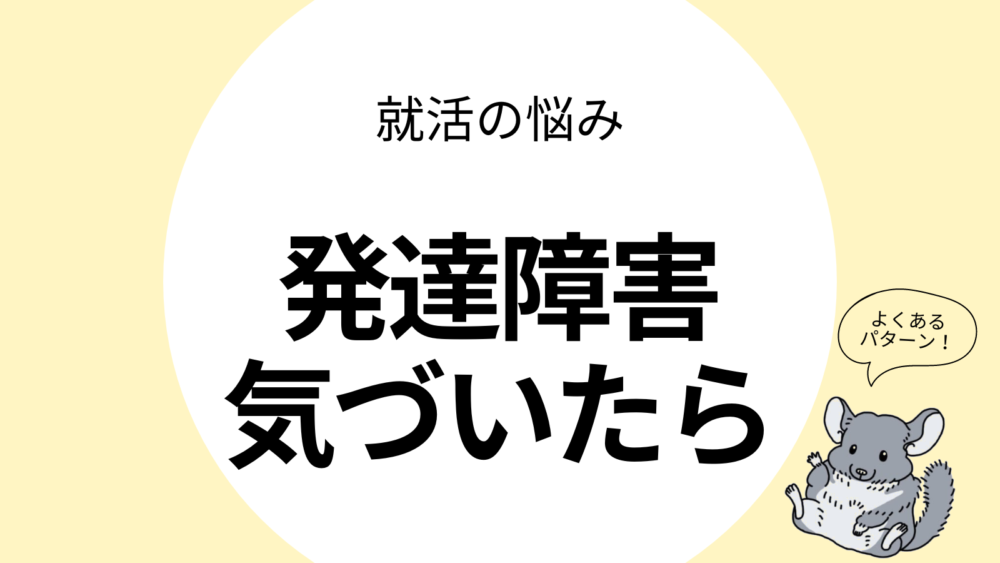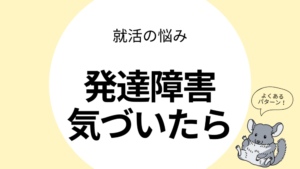- 面接で自分の長所や短所をうまく説明できない
- エントリーシートの作成に時間がかかりすぎて焦る
- 他の就活生と比べて、自分だけが上手くいかないように感じる
就活を進めていくにつれて、発達障害に気づくケースは少なくありません。
企業から内定が出ずに焦ったり、普段は気づかなかった困りごとと直面したりする人もいるでしょう。
 よしだ
よしだ就活で違和感を覚える人は結構いるよ!


本記事では就活で違和感を覚え、発達障害に気づいた方への対処法を3つ紹介します。
まずはご自身の特性を理解し、適切なサポートを受けることが大切。一度立ち止まって、今後の方針を考えてから動きましょう。
- 「内定が全然出なくてやばい」
- 「発達障害って診断されて不安」
こんな方は本記事を、ぜひ最後までお読みください。
就職活動で発達障害に気づくケース


就職活動を進めるにあたり、自分の特性や発達障害に気づく場合があります。
就活は日常生活と異なる環境のため、普段は気づきにくい特性が浮き彫りになることも多いです。
- スケジュール管理
- コミュニケーション
- 書類作成
「うまくいかない」「違和感がある」と感じたら、無視せず状況を整理することが大切です。



なんとなくの違和感を無視しない!
新卒の就活でうまくいかない
新卒の就活では、多くの学生が同じようなスケジュールで活動します。周囲の就活生と比べ、何かおかしいと感じることもあるでしょう。
困難に直面することで、初めて発達障害の傾向に気づく人も少なくありません。
慣れない就活に戸惑っているだけの場合もあるため、不調が頻発するようなら対策を考えましょう。
離職後の再就職で違和感を覚える
一度就職した後に離職し、再就職を進めるなかで発達障害に気づくケースもあります。
前職での経験を振り返る中で、より客観的に自分を見つめられるようになるためです。
- 職場での人間関係の困難
- 指示理解や優先順位付けの難しさ
- 感覚過敏による職場環境への不適応
例えば、「なぜか同僚とうまくいかない」「締め切りに間に合わない」「オフィスの音や匂いが苦手」といった経験が、自分の特性を理解するきっかけとなることがあります。
違和感が必ず発達障害となるわけではありませんが、日常生活でも同様の困難を感じる場合は、障害者支援への相談を検討しましょう。
再就職で違和感を感じたら、まずは特性と向き合って、働き方や方針を決めることが大切です。
就活中に発達障害に気づいた際の対処法3つ


就活中に発達障害に気づいたら、焦ったり不安を感じるかもしれません。
まずは適切な対処法を知り、就職活動の方針を決めなおすことをオススメします。
ここでは、発達障害に気づいた際の具体的な対処法を3つご紹介します。
- 自分の障害特性を把握する
- 障害の開示・非開示を決める
- 企業にどんな配慮を求めるか考える
自分の障害特性を把握する
まず、自分の障害特性を把握しましょう。発達障害には様々な種類があり、それぞれに特徴があります。
| 障害名 | よくある特徴 |
|---|---|
| ADHD | 集中力が続かない 衝動的な行動をとりやすい |
| ASD | コミュニケーションが苦手 特定の分野に強い興味を持つ |
| LD | 読み書きや計算が苦手 |
一般的には上記のように言われていますが、実際は人それぞれ。一人ひとり異なるため、自己理解が大切になります。
特性を把握するうえで重視する点は、特徴よりも仕事にどう影響するか?です。
- 自分の特性はどんな業務と適合しにくいか?
- どんな職種なら苦手な業務が少なくて済む?
- どんなサポートを受ければ働きやすくなる?
障害特性によって、できるだけ不利益を被らないよう、「知ることと今後の対策」はセットで考えましょう。
難しければ、就労移行支援などの支援機関に頼ってみるのも有効です。
筆者は自身が発達障害であることに気付けず、20代のほぼ全てを「相性の悪い仕事」に費やしました。結果として職場から評価される機会はなく、短期離職を繰り返していた時期も長かったです。障害の開示・非開示に問わず、まずは自分の特性や傾向を把握しておくことが非常に大切です。
障害の開示・非開示を決める
就活を進めていく場合、企業側へ発達障害を開示するか、開示しないかを決めましょう。
ご自身の特性や希望職種、就職活動の進み具合などを合わせて、慎重に判断してください。
| 発達障害の情報 | 開示(オープン就労) | 非開示(クローズ就労) |
|---|---|---|
| メリット | 障害を認知してもらえる | 職業選択の幅が広い |
| デメリット | 待遇が悪いケースがある | 配慮や理解が得られない |
上記のメリット・デメリットはあくまでも一例。ご自身で一般枠と障害者枠の求人票を比較したり、希望とマッチした求人があるか確認したりすることが大切です。
発達障害だからといって、必ずしも障害をオープンにする必要はありません。障害特性が仕事に影響しにくい場合、クローズで働く選択肢も十分に考えられます。
例)物事に没頭しやすいタイプだが、目の前の業務に集中できるプログラマーであれば大きな問題なりにくい。
障害の開示は特性を理解したうえで、よりご自身にとって働きやすい方を選びましょう。
企業にどんな配慮を求めるか考える
障害を開示する場合は、企業へ「どんな配慮を求めるか」を考えましょう。
単に発達障害があることだけを伝えるのではなく、障害があることによってどんなサポートを受けたら働きやすいかを明確にしてください。
例えば以下の通りです。
- 明確で具体的な指示
- 静かな環境の確保
- 定期的な休憩時間
自分にとって必要な配慮を明確にすることで、企業側も適切な対応を検討しやすくなります。
ご自身で対処できることは実践し、自分だけではカバーしきれない特性のみサポートを受けることが大切です。
企業に求める配慮事項については、以下の記事で詳しく説明しています。


発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?
- 自己分析が進まない → 自分の強みが分からない
- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない
- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配
こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼りましょう!
- 書類添削+面接対策で合格率UP
- 特性に合う求人を一緒に選べる
- 日程調整や企業とのやりとりを代行
もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?



方向性の相談だけでもOK。初めてなら「dodaチャレンジ」がオススメだよ!
\ 発達障害の当事者が厳選! /
発達障害グレーゾーンの就活ポイント
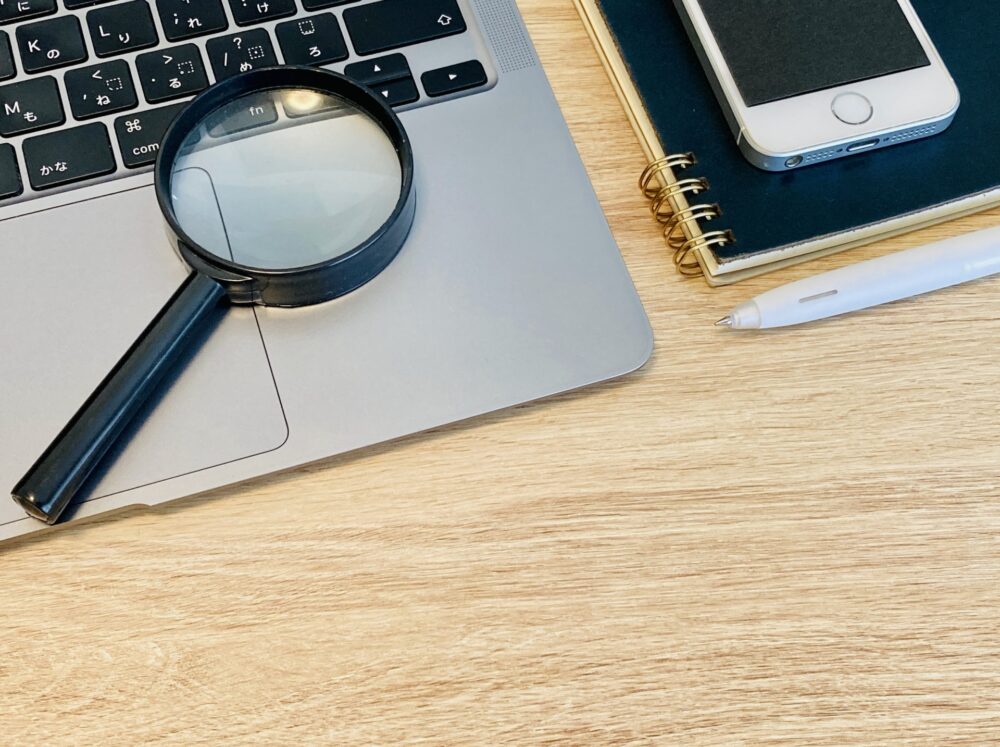
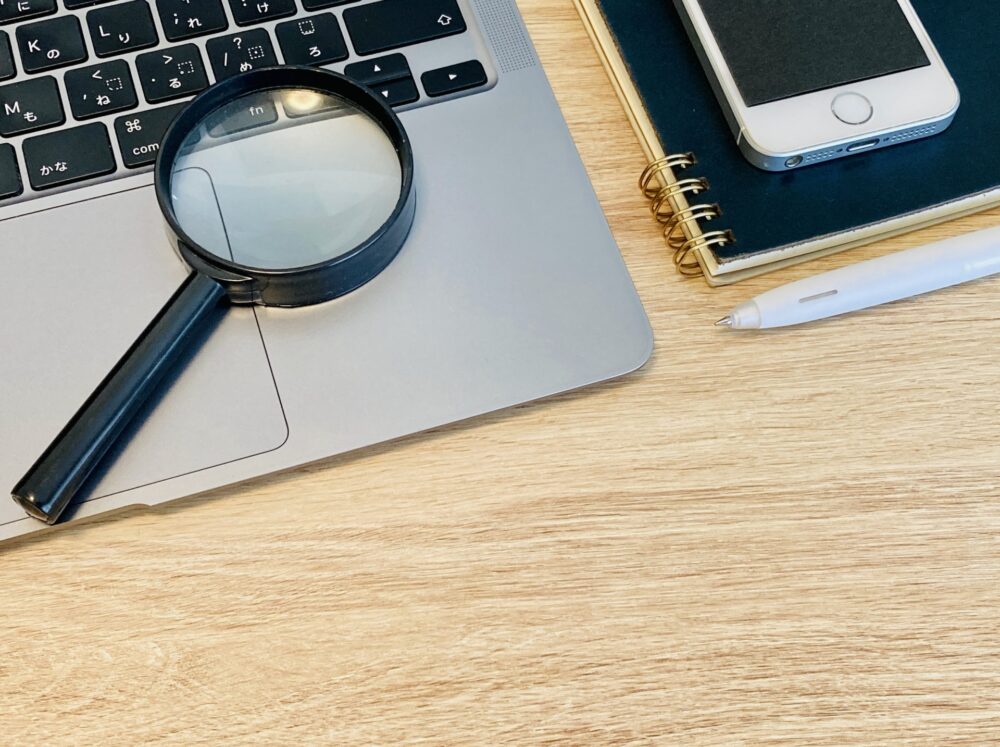
発達障害の診断まで至らなかった「グレーゾーン」の方の場合、就活のポイントは以下の通りです。
- 自己分析と特性の把握
- 適切な職種選び
- 就活サポートの活用
まずはご自身の特性や、向き不向きなどの自己分析が大切です。自分の得意なことや苦手なことを客観的に理解し、就職活動に活かしましょう。
例えば「細部に気を配れる」と気付いたら、ルーティンワークや調整業務の要素を持つ職種・業界と相性がいい可能性があります。
「人とのコミュニケーションが難しい」傾向があれば、対人業務の少ない職種に絞ることも有効です。
自己分析を深めることで、面接時により適切なアピールもできるようになるでしょう。



「できない」よりも「できる」に目を向けるのがオススメ
就活がうまくいかない場合、就活サポートを活用するのもオススメ。学校のキャリアセンターだけでなく、発達障害向けの支援機関や、就活エージェントなども使えます。
就活の進み具合やご自身の体調などと照らし合わせて、状況に合ったサービスを使いましょう。
障害者支援とのつながりを作る


就活中に発達障害と気づいた場合、就職後のために「障害者支援とのつながり」を作ることをオススメします。
- 地域障害者職業センター
- ハローワーク専門援助部門
- 障害者就業・生活支援センター
障害のオープン・クローズにかかわらず、働き始めたら生活リズムが大きく変わります。体調変化や、障害との付き合い方に悩む場面もあるかもしれません。
困ったときに相談できる社外の施設や、コネクションを確保しておくことが大切です。
メンタル面の不調や短期離職を防ぐためにも、早めに障害者支援とのつながりを確保してください。



社内には相談しにくいことも話せるのが良いところ
就活・転職エージェントを使うのもオススメ


就活で内定がもらえず苦戦している方は、就活エージェントや転職エージェントの利用をオススメします。
| 就活エージェント | 学生・新卒 |
|---|---|
| 転職エージェント | 既卒・社会人経験者 |
就活・転職エージェントとは、求職者と企業の間に立ち、就活のサポートをするサービスのこと。求人紹介だけでなく、以下のサポートが無料で受けられます。
- キャリアカウンセリング
- 応募書類の添削・アドバイス
- 模擬面接による面接練習
- 企業とのスケジュール調整
- 待遇面の交渉・アフターフォロー
障害者手帳を取得した方は「障害者向け転職エージェント」を、グレーゾーンの方やクローズ就労の方は「一般向け転職エージェント」を利用してください。
学生の方の場合は、「新卒向け就活エージェント」もあります。
ご自身の状況に合ったエージェントへ登録し、サポートを受けましょう。



就活がうまくいかない人はチェック!
就活で発達障害に気づいたら一人で無理しない
本記事では、就活中に発達障害と気づいたときの対処法について紹介しました。
- 自分の特性を把握する
- 障害の開示・非開示を決める
- 企業へ求める配慮事項を考える
就活中に発達障害の可能性に気づいた場合、むやみに動かず今後の方針を決めるところから始めましょう。
必要に応じて専門の支援機関に頼り、サポートを受けながら就活を進めていくことも大切です。
重要なのは、自分の特性を把握すること。「自己理解」を深めることで、より自分に適した戦略を決められます。
一人で就活を進めるのが難しい場合、就活・転職エージェントを頼ってみるといいでしょう。