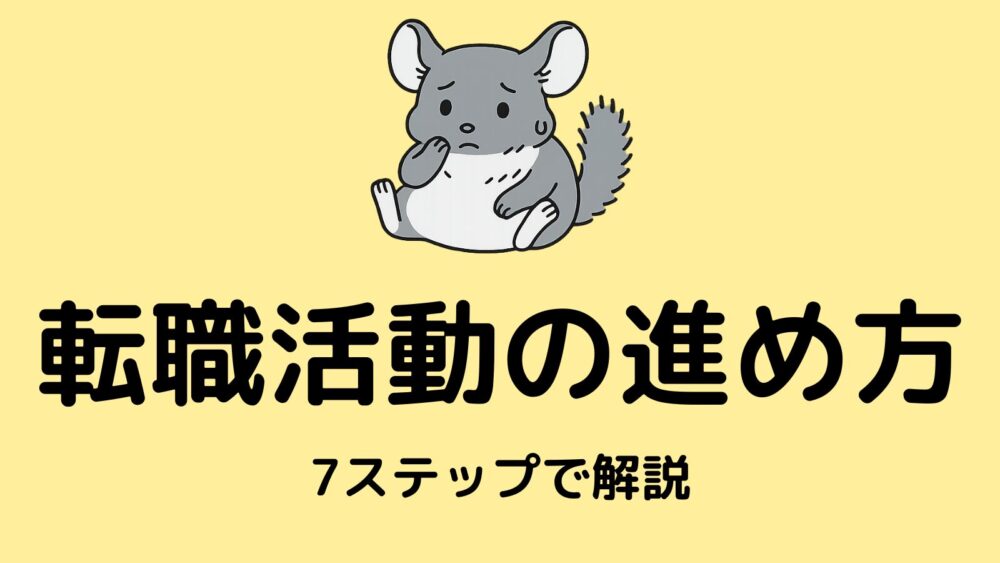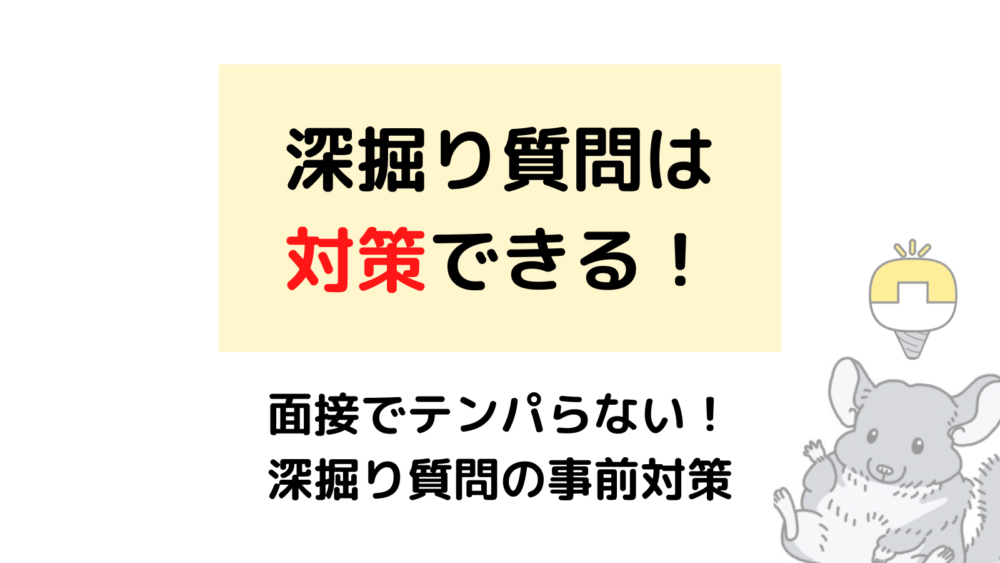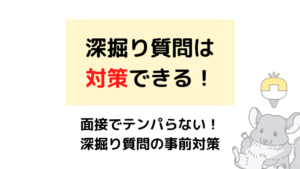- 面接でいろいろ突っ込まれたら答えられるかな…
- 想定外の質問が来たとき、頭が真っ白になるかも
- 面接前にどこまで準備しておけばいいだろう?
面接では、一度答えた内容をさらに掘り下げられる「深掘り質問」がよくあります。
深掘り質問は、あなたの考え方や価値観を知るために聞くことが多いです。スキルや経歴だけでは分からない「人となり」を見ようとしています。
とはいえ想定外の角度から質問されると、答えに詰まったり、焦って話しすぎたりすることも少なくありません。
 よしだ
よしだ私も答えに詰まって焦ったことがある!




この記事では、深掘り質問に慌てず対応するための対処法と、事前準備のポイントを紹介します。
発達障害がある人のなかには、「深掘り質問」に以下のような苦手意識を感じることが多いです。
- 臨機応変に回答する
- 頭の中を整理して言葉にする
- 核心を突くような質問を受ける
深掘り質問は「What・Why・How」の3つの視点で整理しておくと、想定外の質問にも落ち着いて対応できます。
面接を目前にして不安がある方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
面接の深掘り質問とは人物像を知るための確認


面接でよく聞かれる「深掘り質問」とは、あなたの人物像を深く知るためのもの。
スキルや経歴だけでは分からない考え方や価値観、仕事への向き合い方など、その人らしさを把握する目的で行われます。
たとえば「チームで頑張った経験はありますか?」という問いに「○○のときに〜」と答えると、「なぜそのやり方を選んだんですか?」や「そこで一番工夫したことは?」のように、次々と追加で掘り下げられるような流れになります。
発達障害がある人の中には、質問の意図をつかみにくかったり、考えを言葉にするのに時間がかかったりする人もいます。
だからこそ、どのように掘り下げられやすいかを知っておけば、面接で落ち着いて答えやすくなります。



大まかな深掘りの傾向をつかんでおこう!
発達障害のある人が深掘り質問で困りやすい理由


深掘り質問はただ答えるだけでなく、意図を読み取りながら整理して話す力が求められます。
たとえば「どうしてそのやり方を選んだの?」というような、質問の意図が見えにくい場合は、「どこまで答えたらいいんだろう…」と混乱しやすくなります。
特性や思考の癖によっては、非常に答えにくいと感じることもあるでしょう。
- 質問の意図を読み取るのに時間がかかる
- 話す内容を一度に整理するのが苦手
- 頭の中で言葉が渋滞して、詰まってしまう
結果として面接官の聞きたいこととズレてしまったり、長々と説明してしまったりするケースがあります。



私も掘り下げられるの苦手…
深掘り質問には3つの視点で事前準備


深掘り質問に備えるうえで大切なのは、「どんな聞かれ方をするか」を事前に想定しておくこと。
ひとつのトピックに対して掘り下げられるため、傾向が分かれば想定外の質問でも落ち着いて対応できます。
具体的には、What・Why・Howの3つの視点に分けて考えるのがオススメ。
- What(何をしたのか)
- Why(なぜそうしたのか)
- How(どうやったのか)
自分の経験をこの3つに沿って整理しておけば、どこを深掘られても軸がブレにくくなります。



よくあるパターンの把握は大事!
What:経験・取り組み
深掘り質問では、どんな経験をしてきたのかをよく聞かれます。 前職の経歴に合わせて、「この会社ではどのような経験をされましたか?」といった内容で掘り下げられるケースが多いです。
答えやすくするには「キャリアの棚卸し」を行い、職歴と実務経験を洗い出しておくのが良いでしょう。 合わせて以下も整理しておくと、内容に説得力が出ます。
- 部署やチームの人数
- 担当した年数
- 主な役割・担当
全部を完璧に話せなくても、要点を押さえておくだけでグッと話しやすくなります。
Why:理由・考え方
行動やエピソードに対して、理由や考え方を問われる場合もあります。「現職の経験や役割」のエピソードに対して、「なぜ転職をご検討されているのですか?」といった質問です。
「なぜ」の質問には、行動や経験だけでなく、背景にある考え方や判断の軸を知りたい意図があります。
- 物事をどう捉え、どう判断する傾向があるのか
- 働くうえで何を大切にしているのか(価値観)
- 状況をどう見極めて意思決定するタイプか
このあたりが言葉にできていると、単なる事実以上に「その人らしさ」が伝わります。
正解がある質問ではないので、自分の中で納得できる理由を整理しておくことが大切です。
How:手順・方法
行動だけでなく、「どのように取り組んだか」も深掘りされやすいポイントです。
取り組みの中で、どんな工夫をしたかを聞かれることがあります。
たとえば「新しい業務を任された」というエピソードに対して、「引き継で工夫したことはありますか?」といった形です。
他にも課題やトラブルに対し、どう乗り越えたか?もHOWを問う深掘り質問です。
このケースでは、対応の仕方や再現性について確認されていると考えましょう。ポイントを簡潔にまとめて伝えるだけでも、十分に理解を得られます。
面接で深掘り質問が来たときの対処法3つ


深掘り質問は、たとえ準備していても想定外の角度から飛んでくることがあります。
そんなときに慌てず対応できるように、質問の受け止め方や答え方のコツをあらかじめ持っておくことが大切です。
- 焦って答えず、考えを整理してから話す
- 深掘り質問の意図を想像してから答える
- 情報は1つずつ、短く伝える意識を持つ



答え方のコツを知っておけば、怖くない!
焦って答えず、考えを整理してから話す
予想していない質問に焦ったときは即答せず、考えを整理してから話すことをオススメします。
少し間をとってから話し始めるだけで、失言や余計な一言を抑えられます。
- 姿勢を正して深呼吸する
- 伝えたい言葉を頭に浮かべる
- 意識してゆっくりと話す
焦りを受け入れて対策をパターン化することで、気持ちが落ち着きやすくなります。
予想外の質問が不安な方は、別記事「面接対策まとめ」の、困ったときの対処法も参考にしてください。
深掘り質問の意図を想像してから答える
深掘り質問にどう回答するか迷った場合、なぜこの質問を聞かれたのか?と想像してみるのも有効です。
面接官の意図を意識することで、的外れな回答を防ぎやすくなります。
深掘りして聞きたいトピックには、面接官が「知りたいポイント」があると予想できます。
たとえば「お伺いした前職の業務では、どのような工夫をされましたか?」と掘り下げた場合、業務改善の意識や、効率化の考えについて聞きたいのかな?と予想できます。
質問の意図に沿った答えは、伝わりやすく評価されやすいです。
面接官も「知りたいポイント」のために何度も聞き直さずに済み、やりとりがスムーズになります。
情報は1つずつ、短く伝える意識を持つ
深掘り質問に答えるとき、「あれもこれも伝えなきゃ」と話が長くなりやすいです。
しかし一度にたくさん話すよりも、1つのポイントに絞って簡潔に伝える方が、相手に届きやすくなります。
たとえば「この業務で工夫したことはありますか?」と聞かれたときに、成果も工夫も同時に盛り込もうとすると、話の焦点がぼやけてしまいます。「特に意識していたことは○○です」と、1つに絞って話す意識を持つと、相手も理解しやすくなります。
足りなければさらに質問を受ければいいと思えば、気が楽になります。
無理に全部話そうとせず、「足りなければまた聞かれる」くらいの気持ちでいることが、落ち着いたやりとりにつながります。


発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?
- 自己分析が進まない → 自分の強みが分からない
- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない
- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配
こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼りましょう!
- 書類添削+面接対策で合格率UP
- 特性に合う求人を一緒に選べる
- 日程調整や企業とのやりとりを代行
もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?



方向性の相談だけでもOK。初めてなら「dodaチャレンジ」がオススメだよ!
\ 発達障害の当事者が厳選! /
深掘り質問の具体例


筆者が実際の面接で聞かれた質問をもとに、深掘り質問のやりとりを再現しました。
自分の経験と照らし合わせながら、「自分が聞かれたらどう答えるか?」を考えるヒントにしてみてください。
【質問】
前職は〇〇だったとのことですが、具体的にどのような業務を担当していましたか?
【回答例】
○○社では営業職として新規開拓と既存顧客対応を担当していました。特に新規訪問の際は、事前に業界情報を調べた上で、相手に合わせた提案を意識していました。
【深掘り質問(上記の回答に対して)】
その中で、特に工夫したことがあれば教えてください。
【回答例】
提案書の作成時に、相手の業種や過去の導入事例に合わせて資料をカスタマイズするようにしていました。ひと手間加えることで、提案の説得力が増し、成約につながったこともあります。



深掘りからの、追加で深掘りもあったよ…
深掘り質問に詰まったときのリカバリー対応


どれだけ準備をしていても、深掘り質問に詰まってしまうことはあります。
もし答えに詰まったとしても、焦って無理に答えようとするより、丁寧に対応することのほうが大切です。
たとえば質問の意図がつかめなかった場合は、「確認ですが、○○という意味でお聞きしていますか?」のように聞き返して問題ありません。不安であれば「少し考えてもよろしいですか?」と伝えるだけでも、自分のペースを取り戻せます。
面接官が見ているのは「正解」ではなく、私たちの価値観や考え方。
無理に取りつくろって話すのではなく、自分なりの言葉で誠実に伝えることを意識しましょう。



伝えようとする姿勢が大事だよ!
深掘り質問に強くなる考え方


深掘り質問が苦手だと感じるときは、「どう答えるか」だけでなく、どんな意識で面接に臨むかも大切です。
- 深掘り質問は必ず来るものと意識する
- 自己分析で経歴や価値観を整理する
- 「正解」を探すよりも自分の言葉で答える姿勢を持つ



「聞かれる」と分かっていれば怖くない!
深掘り質問は必ず来るものと意識する
面接ではどんな質問に対しても、深掘りされる前提で準備しておくことが大切です。
「掘り下げられるかも?」と意識していれば、実際に聞かれたときにも落ち着いて対応しやすくなります。
- 落ち着いて対応しやすくなる
- 「聞かれる前提」で準備できる
- 深掘りされるのは関心がある証拠
深掘り質問は単なる好奇心ではなく、採用に必要な情報を把握する「見極め」の一環。準備ができていれば、落ち着いて伝えるだけでしっかり評価につながります。
自己分析で経歴や価値観を整理する
深掘り質問に答えるうえで、自分の中にある情報をあらかじめ整理しておくことが大切です。
職歴やエピソードだけでなく、価値観や考え方といった「転職の軸」も見直しておきましょう。具体的な質問に対しても、ブレずに答えやすくなります。
- これまでの経験や役割を洗い出す
- 得意なこと・苦手なことを整理する
- 働くうえで大切にしたい価値観を言語化する
準備の段階で「自分ってこういう考え方をするんだ」と気づいておくことが大切です。
考え方の軸が見えていれば、WhyやHowの質問にも自信を持って答えやすくなります。
詳しいやり方は、別記事「自己分析のやり方まとめ」でも紹介しています。こちらもあわせてお読みください。
「正解」を探すよりも自分の言葉で答える姿勢を持つ
深掘り質問に答えるときに「正解を探さなきゃ」と思いすぎると、かえって言葉が出にくくなることがあります。
大切なのは模範解答よりも、自分の考えや感じたことをそのまま伝える意識です。
- 実体験に基づいたエピソードを交えると説得力が増す
- 多少詰まっても、自分の言葉で丁寧に話すことが印象に残る
- 価値観や判断の背景を加えると、面接官に伝わりやすい
面接では、完璧な回答よりも「その人らしい価値観や考え方」を見られます。
だからこそうまく話すより、自分の言葉で伝えようとする姿勢の方が大切です。
まとめ|深掘り質問は自分の言葉で答えることが大切
この記事では、面接での深掘り質問にうまく対応するための考え方と準備方法について解説しました。
- 深掘り質問は人物像の確認
- 3つの視点で事前に整理する
- 詰まっても丁寧な対応が大切
大切なのは、完璧に話すことより「自分の考えを自分の言葉で伝えよう」とする姿勢です。自己分析を改めて見直しつつ、深掘り質問に備えておきましょう。
「何を話せばいいか分からない」と感じている方も、経験や考え方を整理するだけで伝えやすくなります。



しっかり対策してから面接を受けよう!
面接全体の対策については、以下の記事も参考にしてみてください。
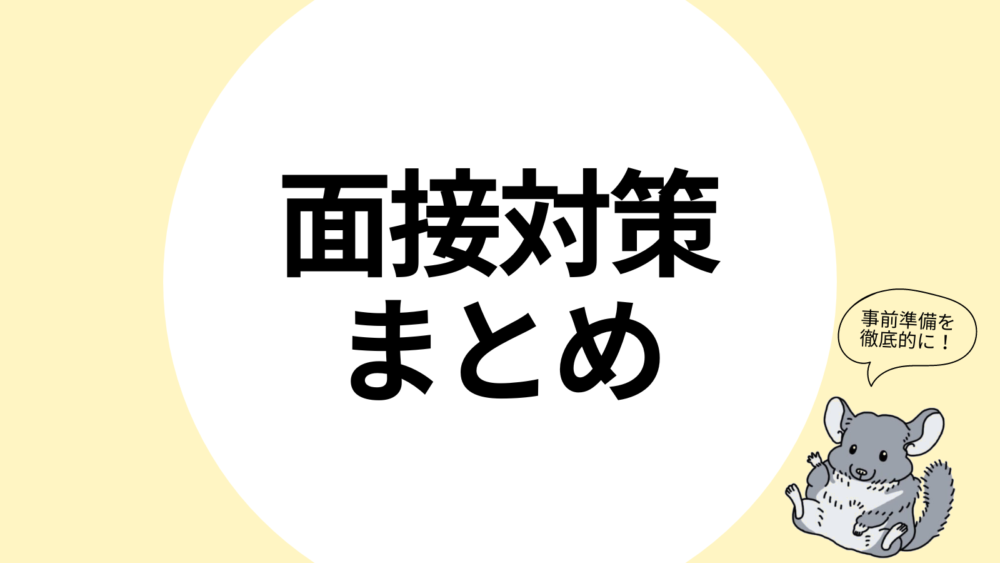
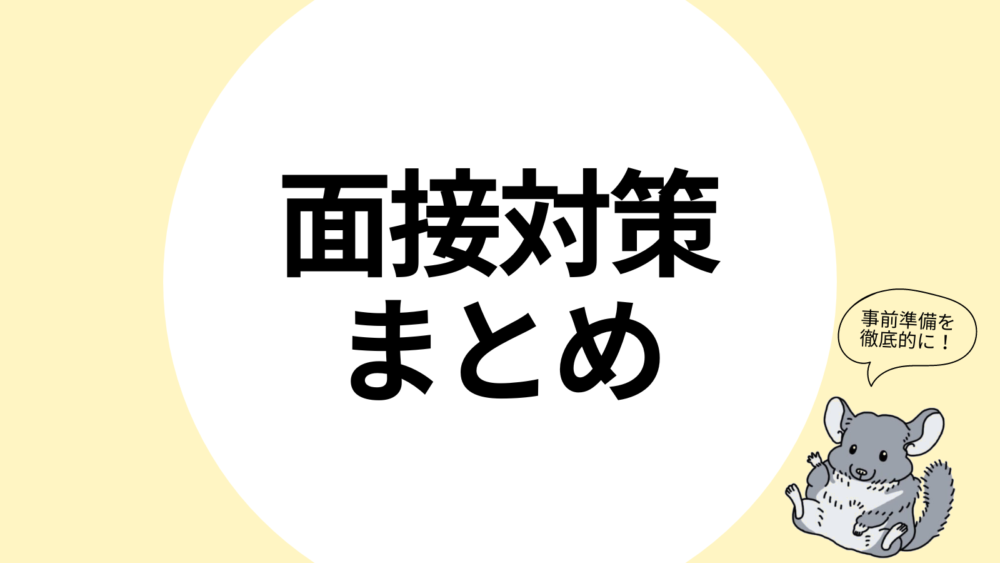


発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?
- 自己分析が進まない → 自分の強みが分からない
- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない
- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配
こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼りましょう!
- 書類添削+面接対策で合格率UP
- 特性に合う求人を一緒に選べる
- 日程調整や企業とのやりとりを代行
もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?



方向性の相談だけでもOK。初めてなら「dodaチャレンジ」がオススメだよ!
\ 発達障害の当事者が厳選! /