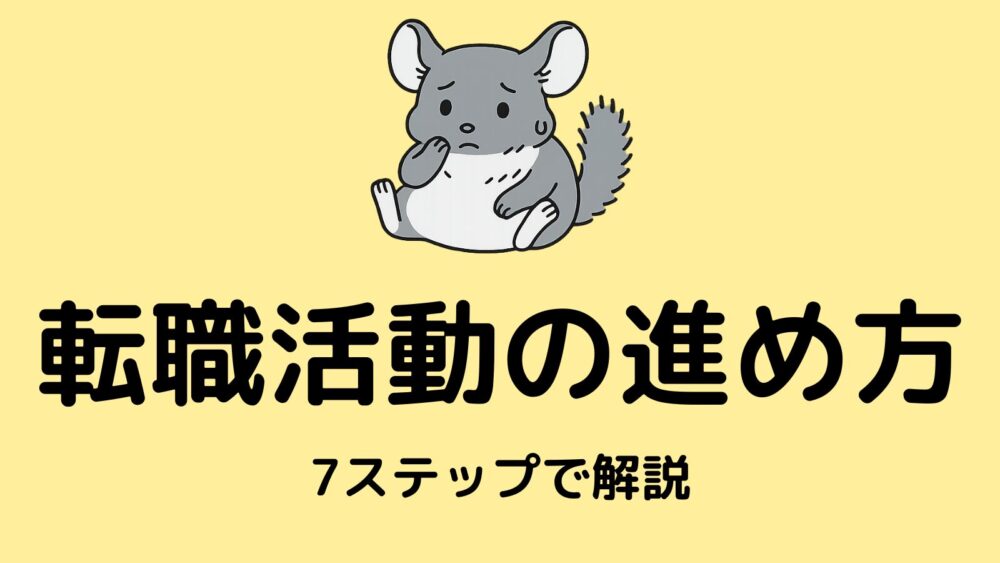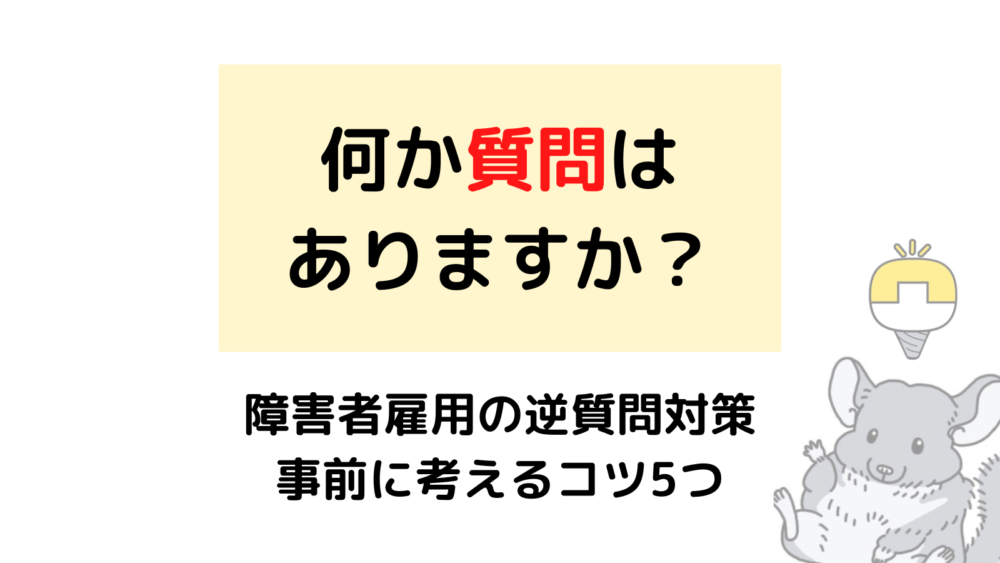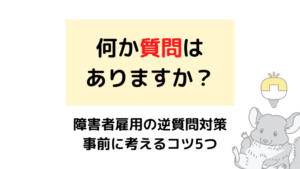- 逆質問って何を聞いたらいいのか分からない…
- 変なことを質問して評価を下げてしまうのは避けたい
- 企業との認識がズレたまま、入社後に苦しむのは嫌!
面接の最後に「何か質問はありますか?」と企業から聞かれる、いわゆる「逆質問」。何を確認すれば良いのか、どう聞けば失礼にならないのか、悩む人は多いです。
事前に逆質問の対策をしておかないと、聞きたいことが思いつかず「ウチに興味ないのかな」と受け取られてしまう可能性もあります。
 よしだ
よしだ手帳にメモして持参するのがオススメ!


本記事では、面接の逆質問を成功させるための5つのコツを中心に解説。具体的な質問例文やNG例、準備のポイントも併せて紹介します。
逆質問では、企業側との認識をすり合わせすることが重要。質問内容をしっかり練ることで、入社後のギャップを減らせます。
本記事を参考にすることで、それぞれの求人に合った逆質問を考えられるようになるでしょう。
面接で失敗したくない、自分に本当に合った環境で働きたい方は、ぜひ本記事を最後までお読みください。
発達障害のある人にとって「逆質問」が重要な理由


転職面接の最後には、ほぼ必ず「何か質問はありますか?」と尋ねられます。いわゆる「逆質問」と呼ばれ、疑問を解消するための大切な機会です。
逆質問は企業との認識を合わせるための、面接における最後のチャンス。入社意欲を効果的に伝えたり、会社の雰囲気や働く環境を確認したりできます。
逆質問によって業務内容の認識ズレを防いだり、企業側の配慮に関する考え方を知る場としても利用しましょう。
- 入社意欲が高いことを伝えたい
- 会社の雰囲気や環境が知りたい
- 業務認識のズレがないか知りたい
特に発達障害がある方にとっては、この逆質問が非常に重要。働きやすさに直結する配慮や、職場環境について具体的に確認できるタイミングになります。
逆質問の時間を有効に使うためには、事前の対策が欠かせません。
しっかり準備することで、入社後のミスマッチを防ぎ、安心して長く働ける環境かを見極めやすくなります。
逆質問は面接終盤の限られた時間で行われます。多くの質問を長々とするのではなく、要点を絞ってコンパクトに確認することを心がけてください。



アピールもいいけど、ゴリ押しすると逆に引かれちゃうかも!
逆質問への準備と当日のポイント


逆質問は、面接の終盤に与えられる貴重なやり取りの時間です。緊張しやすい場面でもあるため、事前に準備をしておくことで落ち着いて対応できるようになります。
質問内容はできるだけ複数用意し、手帳やメモに書いておくと安心です。面接中に疑問が解消された場合の伝え方や、逆質問のあとの一言も、印象を左右するポイントになります。
このパートでは、逆質問に向けた準備のコツと当日の対応ポイントを具体的に紹介します。



聞こうと思ってた質問が途中で解決しちゃったらテンパるよね〜。
逆質問は複数準備してメモに残す
逆質問は、企業とのミスマッチを防ぎ、自分らしく働くための重要なやり取りです。とはいえ、本番で緊張してうまく質問できなかったり、用意した内容を忘れてしまうこともあります。
だからこそ、できれば3つ以上の質問を事前に考え、メモに残しておきましょう。
あらかじめメモを用意しておけば、安心して面接に集中できます。
「最後に何か質問はありますか?」と聞かれたら、事前に聞きたいことをメモしてきたことを伝え、手帳を見ながら質問すると良いでしょう。
例)
- 事前に聞きたいことをメモしてきたので、手帳を見ながら質問してもいいでしょうか?
- 質問のお時間を頂きありがとうございます。質問を準備してまいりましたので、見ながら聞いてもいいでしょうか?
また、面接中の説明で新たな疑問が出てきたときは、許可をもらって手帳に書き残しておくと安心です。
頭で覚えず紙に書き残しておくことで、「逆質問で聞きたい」と覚え続ける負荷が減り、目の前のやり取りに集中しやすくなります。
面接中に疑問が解消した場合の伝え方
面接中に企業から詳しい説明があり、用意していた質問がすべて解消してしまうこともあります。
その場合は無理にひねり出そうとせず、質問がないことを丁寧に伝えるだけで問題ありません。
例)
- 丁寧にご説明いただき、私からの質問はすべて解決しました。ありがとうございます。
- ○○について質問しようと考えておりましたが、面接中にご説明いただき、解消されました。ありがとうございました。
- ありがとうございます。気になっていた点をご説明いただけたので、質問はございません。ぜひ御社に貢献させていただければと思います。
逆質問の意図はあくまで確認や意思表示。質問がなくても、お礼や「疑問が解消されたこと」を添えて丁寧に伝えれば、十分に好印象を残せます。
質問が終わったらお礼を忘れずに伝えよう
逆質問が終わったら、最後にお礼のひと言を添えるのを忘れないようにしましょう。
丁寧な印象を与えるだけでなく、「質問はこれで終わり」という区切りを相手に伝えることもできます。
特にオンライン面接では、相手の反応がわかりにくいため、言葉で終わりを明示することで“間”を防ぐ効果もあります。
例)
- 私からの質問は以上です。ありがとうございました。
- 聞きたいことはこちらで全てです。丁寧に答えてくださりありがとうございます。
- お答えくださりありがとうございました。私から聞きたいことは以上です。
このように、お礼とともに逆質問の終了を伝えると、やり取りがスムーズになります。
また、逆質問のあとには今後の採用スケジュールの案内があるケースが多いため、最後まで気を抜かずに対応しましょう。



質問が終わったことを伝えないと、変な間ができてウッとなる…
逆質問を考える5つのコツ【例文で解説】
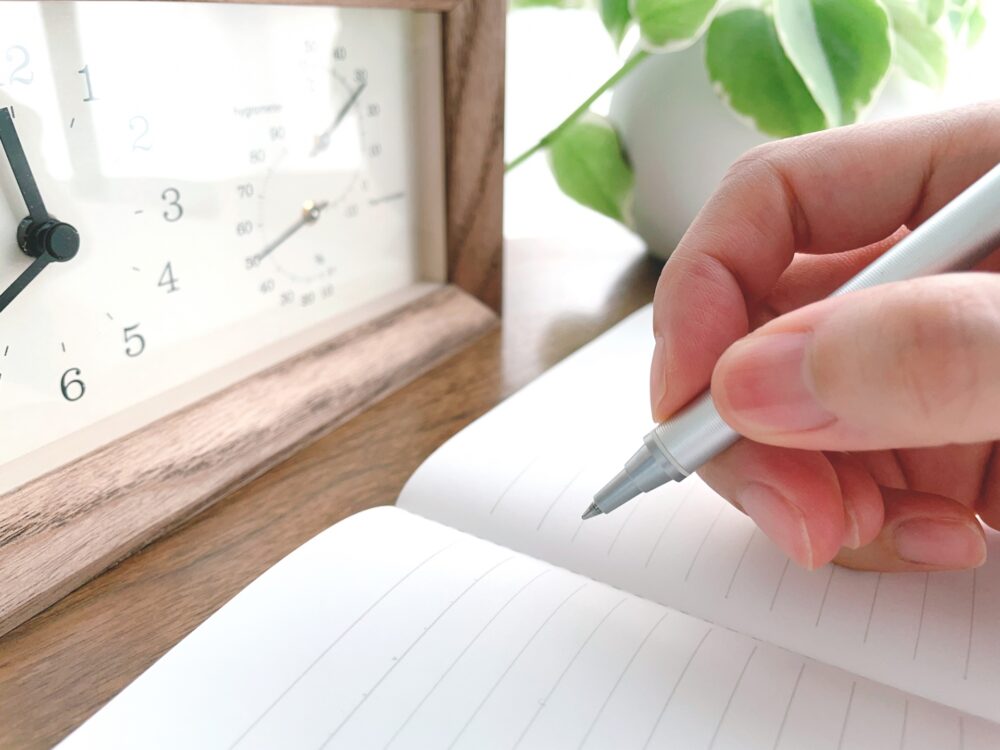
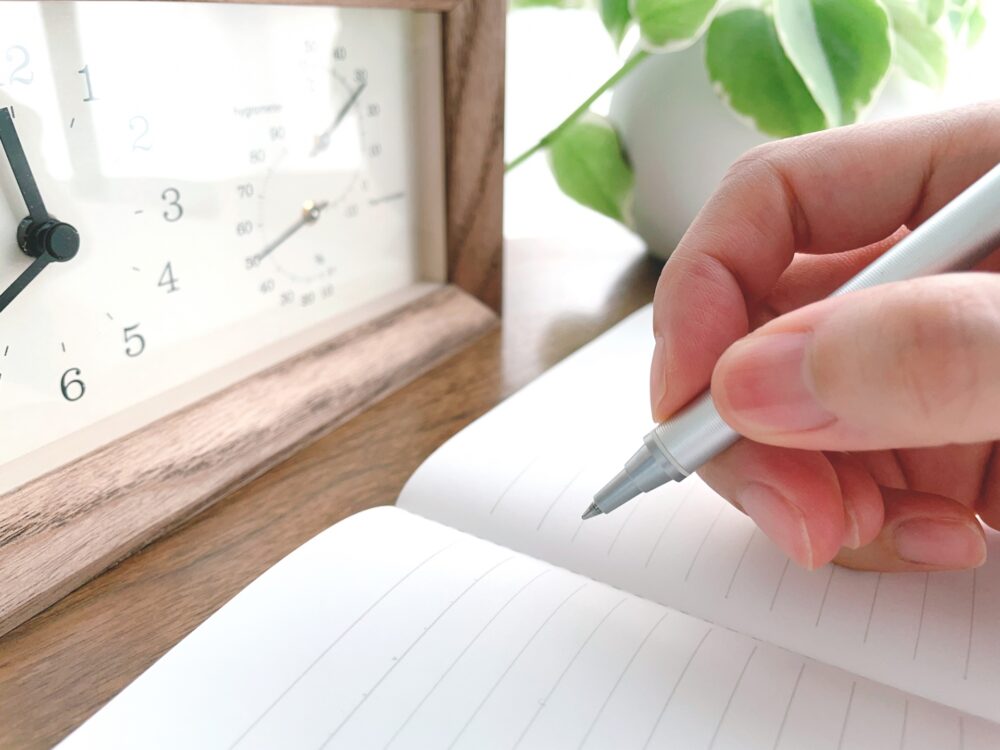
逆質問を考える際は、面接の限られた時間の中で「何を優先的に確認したいか」を明確にしておくことが重要です。
質問の内容は、あなたが何に注目して企業を見ているかを伝えるサインにもなります。
- 業務内容の認識をすり合わせ
- 障害者雇用への価値観
- 面接官から見た社風や雰囲気
- 上司・同僚など配属先の部署
- 企業があなたに求めていること
面接官は逆質問を通して、「この人は働く環境をしっかり見ているな」「職場に馴染みそうだな」といった印象を持つこともあります。
だからこそ、その場で思いついた質問ではなく、事前にしっかり考えた質問を用意しておきましょう。



枕詞に「もし」「仮に」「例えば」なんかを付けて見るのもアリ!
業務内容|認識のズレをなくす質問例
業務内容に関する逆質問は、前向きな姿勢を伝えやすく、面接官にもポジティブな印象を与えます。
- 業務内容を正しく理解しているかの再確認
- 私にどんな業務を遂行してほしいのか
求人票だけでは分かりにくい仕事内容の詳細や、入社後に任される業務のイメージを深掘りして確認しましょう。
特に、どんな仕事を期待されているのか、自分の希望やスキルと合っているかを確認することが大切です。
入社後に業務理解のギャップがあると、モチベーション低下や早期離職につながるリスクもあります。
例)
- もし御社に入社した場合、重点的に担当してほしい業務などはございますか?
- 担当部署の1日の業務スケジュールをお聞きしてもよろしいでしょうか?
- 仕事を覚える際、新人の方はどのような流れで業務に慣れていくのでしょうか?
認識のずれやギャップに耐えきれず、早期離職してしまうのは非常にもったいないです。
業務内容に関する質問は、深く踏み込んでもネガティブな印象になりにくいのが特徴。不安を感じていることがあれば遠慮せず、優先的に確認しておくと安心です。
発達障害への配慮|働きやすさに関する質問例
障害者雇用の場合、企業が発達障害にどのような理解や配慮を持って雇用しているかは、安心して働き続けるうえで重要なポイントです。
採用実績や現場の理解といった浸透レベルや、ステップアップ・キャリア形成などの将来性なども「働きやすさ」に直結します。
なかには、人事部は理解があっても、実際の配属先では特性への配慮が薄いというケースもあります。
このようなミスマッチを防ぐためにも、現場との連携や具体的な支援の有無を確認しておくことが大切です。
例)
- 発達障害を持つ方の雇用実績はありますか?
- 配属部署では障害者雇用の方は何名くらいいますか?
- 障害者雇用の方のキャリアアップ事例はありますか?
実際に働いている方の人数や雇用の様子を聞くことで、職場の受け入れ体制や雰囲気をイメージしやすくなります。
他の方がどのような配慮を受けながら働いているかを知ることは、自分に合った働き方を考えるヒントにもなります。
障害者雇用の扱いや現場での配慮が気になる場合は、深掘りして聞いてみると良いでしょう。
社風・環境|職場の雰囲気を知る質問例
職場の雰囲気や人間関係が自分に合うかどうかは、長く働くうえで重要な要素。社風について質問する際は、「面接官自身の視点」で答えてもらうよう意識してみましょう。
面接官が人事の方なら会社全体の傾向やカルチャーを、現場の上司や配属予定の担当者ならチームの雰囲気を、それぞれの立場から見えるリアルな空気感を確認できます。
例)
- 〇〇さんから見て、御社はどんなタイプの会社だと思いますか?
- 〇〇さんが御社を選んだときの決め手をお聞かせいただけますか?
- 働く中で『ここが御社のいいところだ』と感じたエピソードがあれば教えてください。
社風や雰囲気については、公式サイトなどで紹介されている場合もありますが、「実際に働いている人の視点」は今しか得られない情報です。
会社の雰囲気を重視している方は、前職との違いや自分が合わなかった環境を軽く伝えたうえで、「御社ではどうですか?」と比較する形で聞いてみるのも効果的です。
配属部署・チーム|一緒に働く人に関する質問例
誰と一緒に働くかは、仕事内容と同じくらいか、それ以上に重要です。
特に発達障害がある方にとっては、指示の伝え方や人間関係の築きやすさが、働きやすさに大きく影響します。
配属予定の部署にはどんな人がいて、どのような雰囲気なのか。あらかじめ逆質問で聞いておくことで、入社後の具体的なイメージを持ちやすくなるでしょう。
例)
- 配属される部署には私と似たようなタイプの方はいますか?
- 担当する部署は何名くらいの方が働いていますか?
- 配属先の部署では、どのような考え方や価値観を大切にされていますか?
こうした質問を通じて、チームの人数や構成、働くうえでの空気感がつかめます。人間関係やコミュニケーションスタイルを重視する方にとっては、非常に大事な確認ポイントです。
可能であれば、部署見学やオンラインでの顔合わせを希望してみるのもひとつの方法です。
求める役割|企業側の期待を確認する質問例
今回の募集で企業があなたにどんな役割を期待しているかを確認することは、入社後のギャップを減らすうえで非常に重要です。
転職の場合、採用には必ず目的や背景があります。だからこそ、その意図を逆質問でしっかり深掘りしておくことが大切です。
- 何をしてほしいのか?
- 今までその業務を担当していたのはどんな人か?
- いつ頃までに戦力として期待しているのか?
具体的に、5W1Hで掘り下げて質問してみてください。「求人に対して興味を持っている」とポジティブに受け取ってもらえるでしょう。
5W1Hは、「When:いつ」「Where:どこで」「Who:だれが」「What:何を」「Why:なぜ」「How:どのように」といった英単語の頭文字を取ったもので、伝えたい内容をこの要素に沿って構成すると、情報を整理できるのです。
引用元:kaonavi
例)
- ○○の担当とのことですが、前任者はどんな方でしたか?
- いつ頃までに仕事を独り立ちしてほしいなど目安はありますか?
- 本日お伝えした中で、私に足りない経験やスキルがあればお教えください。
こうした質問は入社後の期待値をすり合わせると同時に、自分の成長意欲や誠実さを伝えることにもつながります。
企業とのズレをなくす意味でも、積極的に確認しておくと安心です。


発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?
- 自己分析が進まない → 自分の強みが分からない
- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない
- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配
こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼りましょう!
- 書類添削+面接対策で合格率UP
- 特性に合う求人を一緒に選べる
- 日程調整や企業とのやりとりを代行
もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?



方向性の相談だけでもOK。初めてなら「dodaチャレンジ」がオススメだよ!
\ 発達障害の当事者が厳選! /
筆者が面接時に使っていた逆質問の例


私が転職活動をしていた頃、よく聞いていた逆質問は「1年後、どんな姿を求めていますか?」です。
この質問をすることで、企業としての価値観を判別できます。
- 企業の障害者雇用に対するスタンスが分かる
- 明確な役割を決めて採用活動をしている
- 長期視点でキャリア形成を考えているか分かる
もし「とりあえず雇っておこう」「とにかく人数が必要」といった雰囲気が感じられる場合、法定雇用率の達成だけが目的かもしれません。
逆に、「こういう役割を担ってほしい」と明確に答えてくれる企業は、長く働ける環境である可能性が高いと感じました。
大切なのは、「面接に受かること」ではなく、安定して自分らしく働ける場所と出会うこと。逆質問の時間は、企業が私たちを見るだけでなく、私たちが企業を見極める時間でもあります。



企業が私たちを見極めるように、私たちも企業を見極めよう!
面接で避けるべきNG逆質問の特徴と具体例


逆質問は「求職者から自由に質問できる時間」ですが、その内容も選考の一部として見られています。質問の仕方や内容によっては、マイナス評価につながることもあるため注意が必要です。
面接官は、あなたの質問を通して「どんなことに関心があるのか」「入社を前向きに考えているのか」などを読み取っています。
だからこそ、逆質問では前向きな意図が伝わる質問を意識しましょう。
以下3点は、逆質問で避けた方がいい内容です。
- 給与・休暇など待遇面の質問
- 調べれば分かる内容の質問
- すでに説明された内容の質問
これらは「受け身な姿勢」「情報収集の不足」「熱意が伝わらない」などの印象を与える可能性があります。



せっかくの質問機会なのに悪印象を持たれるのはもったいないよ!
給与・休暇など待遇面の質問
求人の待遇に関する質問は、逆質問の場では避けた方が無難です。
待遇ばかりを気にする人という印象を与えてしまうと、「この人は仕事への意欲が低いのかな」と受け取られてしまう可能性があります。
特に一次面接では、まだ関係構築の段階。その後も選考が控えているため、待遇よりもミスマッチを防ぐための質問を優先した方が好印象につながります。
例えば、以下のような質問は気を付けましょう。
- 給料
- 福利厚生
- 休暇
NG例)
- 平均的な残業時間はどれくらいですか?
- 有給取得率は高いですか?
- ワークライフバランスは整っていますか?
これらは多くの場合、求人票に記載されているか、内定後に確認できる内容です。
待遇面が気になる気持ちは当然ですが、逆質問の場ではその思いはぐっとこらえて、前向きな話題に集中しましょう。
調べれば分かる内容の質問
企業の公式サイトや求人票を見れば分かるような内容は、逆質問でそのまま聞かないようにしましょう。
聞けば答えてもらえると思いますが、「自分で検索する能力の低い人」という印象を与えてしまうリスクがあります。
以下に関する質問は注意が必要です。
- 事業内容
- 企業の強み
- 業界内の立ち位置
NG例)
- 御社の主軸となる事業はなんでしょうか?
- 私が入社したらどの業務を担当するのでしょうか?
- 業界内ではどんな企業が競合となりますか?
こうした内容は、あらかじめ自分なりに調べたうえで仮説を立て、それを踏まえて深掘りする形が好印象です。
例)
御社の求人を拝見し、私が担当する業務の中では○○と△△が特に重要かと思いました。もし入社した際には○○と△△に力を入れていくという認識で合っていますでしょうか?
このように、情報を踏まえた前向きな質問にすることで、興味や理解度の高さを伝えることができます。
どうしても深掘りが難しい場合は、別の観点での逆質問を考えるのがオススメです。
すでに説明された内容の質問
面接中にすでに説明された内容を、逆質問の時間にもう一度聞いてしまうのは避けましょう。
面接中に話を聞いていなかったと受け取られ、応募に真剣ではないと判断される可能性が高いです。
以下は面接時に説明を受けやすい内容です。
- 業務内容に関する基本的な説明
- 求める人物像についての確認
NG例)
- (説明があったにも関わらず)「事業内容について詳しく教えてください。」
- (説明があったにも関わらず)「仕事内容について教えてください。」
こうした質問は、すでに説明済みの内容であることが多いため、そのまま聞くと「先ほどお伝えしましたが…」という気まずい返答を引き出してしまう可能性があります。
どうしても確認したい場合は、「先ほどのご説明をふまえたうえで、さらに深く理解したい」という姿勢を示すことがポイントです。
例)
先程のお話で自立性のある人が望ましいとお伺いしましたが、具体的にはどのような働き方を想定されているのでしょうか?ぜひ御社に貢献したく、ご認識を詳しくお伺いできればと思います。
このように、説明された内容をベースにして、面接官との認識をすり合わせる形の逆質問ができると好印象です。
聞きにくい質問は転職エージェント経由も有効


残業時間や給料などの待遇面については、面接の場で詳しく聞くと「条件ばかり気にしている人」と思われるリスクがあります。
とはいえ、不安なまま選考を進めるのも避けたいところ。
そんなときは、転職エージェントを通じて企業に確認してもらう方法がオススメです。
- 求人紹介の時点で、すでに企業の内部情報を詳しく聞いていることがある
- 面接中は「自己PR」に集中し、交渉や条件確認は任せられる
- 条件面に関しては、エージェントが企業に交渉してくれる場合もある
自分で聞きにくい内容でも、エージェントが間に立って丁寧に伝えてくれるため、印象を損なわずに情報を得ることができます。
逆質問で無理にすべてを聞き出そうとせず、面接では印象アップに集中し、確認が必要なことは後からエージェントに相談するという流れを意識してみてください。
まとめ|発達障害だからこそ 「逆質問」の相互理解が大事
この記事では「何か質問はありますか?」と聞かれる逆質問の場面について、発達障害のある方に向けた対策と考え方を紹介しました。
- 逆質問は、企業との認識をすり合わせる大切な時間
- 内容によっては、印象を下げてしまう質問もある
- 質問がなければ、無理に絞り出さず丁寧に伝えればOK
逆質問はただの形式的な会話ではなく、あなたの関心や意欲、考え方を伝えるチャンスです。企業にとっても、あなたがどんな環境を求めているのかを知る大切な時間になります。
逆に、応募書類の繰り返しや、調べれば分かる内容ばかりだと、あなたの個性や強みが伝わらないこともあるでしょう。
面接でうまく話せなかったとしても、逆質問を通じてあなたの主張を補足することは可能です。
自分にとって本当に合った職場かどうかを見極めるためにも、事前に逆質問をしっかり準備しておきましょう。


発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?
- 自己分析が進まない → 自分の強みが分からない
- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない
- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配
こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼りましょう!
- 書類添削+面接対策で合格率UP
- 特性に合う求人を一緒に選べる
- 日程調整や企業とのやりとりを代行
もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?



方向性の相談だけでもOK。初めてなら「dodaチャレンジ」がオススメだよ!
\ 発達障害の当事者が厳選! /