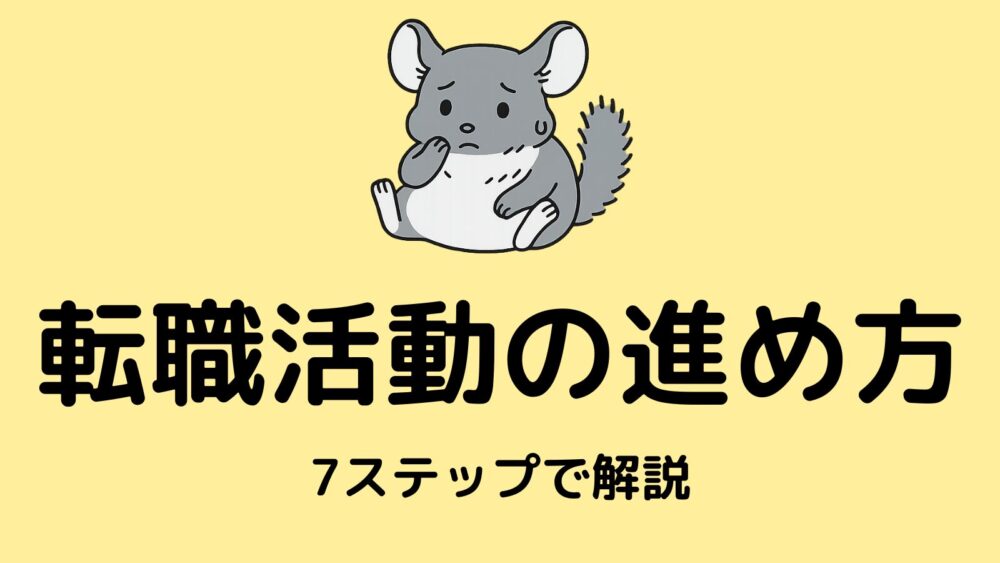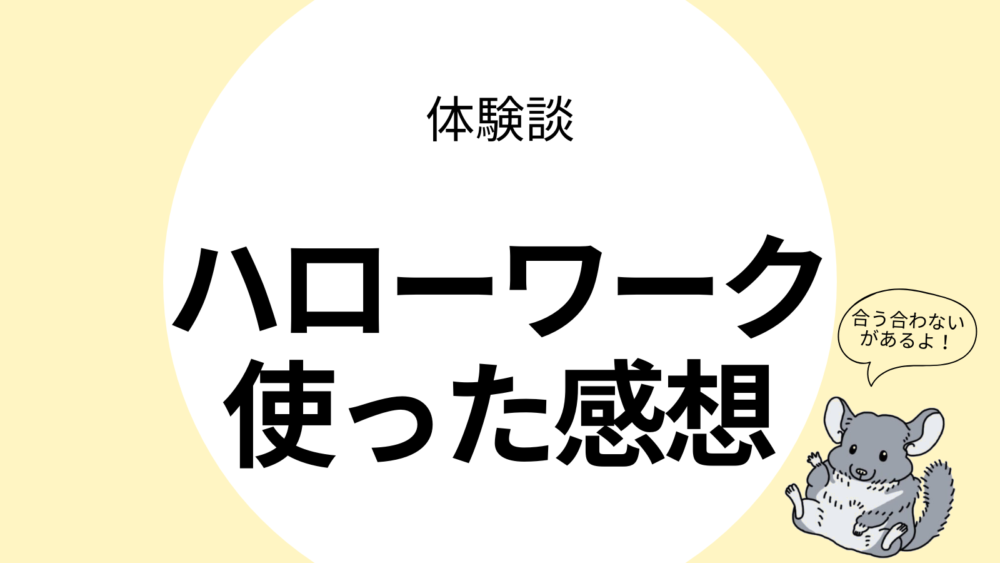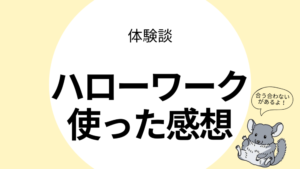- ハローワークって、実際どうなの?
- 求人って、選べるほどある…?
- どんな支援が受けられるの?
私自身そんな疑問を持ちながら、就労継続支援A型から、ハローワーク経由で障害者雇用のパート求人に就職しました。
実際に使ってみると、支援機関との連携や担当者の存在が助けになった一方で、「これは人を選ぶな」と思う点も正直ありました。
 よしだ
よしだ当時のぶっちゃけ話も書いた。




この記事では、A型からハローワークを使って就職した実体験をベースに、過去を振り返りながらお伝えしていきます。
- 実際にどんなサポートを受けられるのか
- 使って感じた「良かったこと」「惜しいポイント」
- ハローワークが合う人・合わない人の違い
障害者雇用でハローワークの利用を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
就労継続支援A型からの就活でハローワークを使った理由


就労継続支援A型では、軽作業を中心に約1年間通っていました。
少しずつ働くペースには慣れてきたものの、時給は最低賃金のまま。もっと収入を増やしたい、勤務時間を伸ばして働きたいという気持ちが強くなり、一般企業への就職を意識し始めました。
ハローワークとの関わりは、A型の利用よりも前から。障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)を通じて担当者とつながりがあり、相談や求人応募にもすでに何度か取り組んでいました。
当時、ハローワーク経由で就職したものの、すぐに辞めてしまった経験があります。そのこともあり、「どうせ選べるような求人なんてない」と思っていたのが正直なところ。
ただ、A型と条件面がほとんど変わらないなら、一般企業にチャレンジしてみてもいいかもしれない。そう思い直し、あらためてハローワークを頼ることにしました。
他にこれといった選択肢も知らず、現実的に動くしかなかったというのが本音です。
実際に使ったハローワークの支援内容


ハローワークでは、障害のある方向けにさまざまな就職支援が行われています。 私自身も、発達障害の特性をふまえた支援を受けながら、いくつかのサポートを利用しました。
- 定期的な面談
- 求人選びや応募先の検討
- 合同面接会
- トライアル雇用
すべてがスムーズだったわけではありませんが、「一人では気づけなかった選択肢」に出会えた経験もありました。
私が実際に受けた、ハローワークのサポート内容をご紹介します。
専門援助部門での定期面談
障害のある方向けに、ハローワークには「専門援助部門」という部署があります。
私もここで、発達障害に詳しい担当者と定期的に面談を行いながら、就職活動を進めていました。
面談では、その時の状況や気になっていることをゆっくりヒアリングしてくれて、無理に急がせるような雰囲気はありませんでした。一方的にアドバイスされるというより、「どう動くかを一緒に考える」スタンスだったのが印象的です。
特にありがたかったのは、スケジュールや行動目標を紙にまとめてくれたこと。
「いつまでに何をするか」「次の面談までに何を決めるか」といった流れが視覚的に整理されていて、頭の中の混乱が少し落ち着きました。
この対応が発達障害向けだったのかは分かりませんが、自分にとっては非常に助かるやりとりでした。
感覚的に、話すより見て理解する方が楽なタイプには、こうした支援は合っていると思います。
ハローワークで紹介される求人の中身
実際に紹介された求人を見たとき、最初に感じたのは「思っていたよりも条件が厳しい」ということでした。
清掃や倉庫内作業といった軽作業系が中心で、時給は最低賃金レベルがほとんど。A型とあまり変わらない条件の求人も多く、期待とのギャップを感じたのを覚えています。
一方で、実務経験が長く求められる求人や、高度なスキルを前提にした職種など、ハードルの高いものも混じっていました。
「これって誰向けなんだろう?」と思うような案件もあり、最初は戸惑いも大きかったです。
ただ、中には自分の希望に近いものもあり、「こういう求人もあるんだな」と感じることもありました。
一人で探すと見落としがちなので、支援機関やハローワークの担当者と一緒に見ていくと、思わぬ発見があるかもしれません。
合同面接会とトライアル雇用
ハローワークでは、障害者雇用に特化した「合同面接会」が定期的に開催されています。
私も参加したことがあり、なかぽつの担当支援者が同行してくれました。
会場の雰囲気としては、企業側も求職者側もある程度“慣れている”感じで、少し独特な空気でした。ただ、私はあえて常連企業っぽくないブースを選んで面接を受けました。
結果的にその企業とは相性が良く、後日二次面接を経て採用が決まりました。担当者がその企業と面識があったことも、話がスムーズに進んだ要因のひとつだったと思います。
また、このときは「トライアル雇用制度」を利用しました。制度自体は使っていましたが、実際の就労にあたって特別な配慮を受けた記憶はあまりなく、自然な流れで職場に馴染んでいった印象です。
支援者と一緒に動いたからこそ、うまくマッチする企業と出会えたと感じています。
ハローワーク経由で採用された仕事とその後


ハローワークを通じて採用されたのは、障害者雇用でパート勤務の事務職。勤務時間は短めでしたが、A型よりも業務内容に幅があり、「一般企業で働く」という実感を得られたのが大きな変化でした。
当初は、フルタイムや正社員登用の可能性もあるとの話で、少しずつ働き方を広げていけたらと期待していました。
実際に勤務時間は徐々に延び、環境にも少しずつ慣れていきました。一方で時給はあまり上がる見込みがなく、期待していた正社員登用も音沙汰なし。将来的な視点で考えると、長く続けるには難しさを感じた覚えがあります。
それでも、「一般企業で働いた経験ができた」という点は、次のステップにつながる自信になりました。
ハローワークと支援機関が連携してくれたことで、就職初期の不安も軽減され、比較的スムーズに職場に馴染むことができたと思います。
ハローワークが合う人・合わない人


ハローワークには、障害のある方向けの支援がありますが、誰にとっても使いやすいとは限りません。
私自身も利用するなかで、「こういう人には合うけど、こういう場面では使いにくいかも」と感じたことが何度もあります。
実際にどんな支援が活用できるかは、働き方や置かれている状況によっても違ってきます。
実体験をもとに、ハローワークが向いていると感じた人と、相性の良くない人の傾向を整理してみました。
ハローワークが合う人の特徴3つ
私自身の体験をふまえて、「こういう人には合いやすい」と感じた特徴をまとめてみました。
①初めての就職やブランク明けの人
職歴が少ない、または働くこと自体に不安がある人にとっては、定期的な面談や支援機関との連携が心強いと感じました。
私の地域では担当者の方との面談予約が取れたので、スケジュールが組みやすかったです。
スモールステップで進めたい場合には、特に有効です。
②就職までの道のりを一緒に整理したい人
「どこから動けばいいのかわからない」「何を準備すべきか分からない」といった状況でも、面談を通じてスケジュールや目標を一緒に組み立ててもらえます。
自分一人では不安なとき、思考整理のサポートとしても役立ちました。
③地域に密着した求人や支援を活用したい人
ハローワークは地域とのつながりが強く、支援機関との連携や、地場の企業とのネットワークもあります。
支援者経由で話がスムーズに進むこともあり、地元で就職を目指す人には合っていると感じました。
転職エージェントをオススメしたい人
ハローワークの支援には良さもありますが、すべての人に合うわけではありません。
私自身、在職中に次の仕事を探す場面では、ハローワークの仕組みが使いにくいと感じた経験があります。
①在職中に転職活動を進めたい人
ハローワークの求人に応募するには窓口での手続きが必要で、開庁時間も平日日中に限られています。
働きながらの利用はハードルが高く、柔軟な対応を求めるなら転職エージェントの方が現実的でした。
②キャリアアップや条件改善を目指す人
私が利用した求人は、全体的に時給や待遇の幅が狭く、スキルを活かして条件を上げたいと考えたときに選択肢が少ないと感じました。
エージェント経由の方が、キャリアの希望に合った求人が見つけやすかったです。
③書類提出や面接調整などのサポートが欲しい人
エージェントは求人紹介だけでなく、応募書類の添削や面接日程の調整なども代行してくれます。
精神的にも負担が少なく、就活のストレスを軽減できた点は大きなメリットでした。
ハローワークを使って感じたこと


ハローワークの支援を受けながら就職活動をしたことで、「思っていたより使える」と感じる場面もありました。
面談で話を整理できたり、支援機関との連携がスムーズに進んだりと、安心して進められるポイントは多かったです。
一方で、求人の質や選択肢の幅に物足りなさを感じたのも事実。実際に応募できる求人は限られていて、希望条件を上げようとすると選択肢が一気に狭まる印象がありました。
支援自体はしっかりしているものの、タイミングや条件が合わないと「動きづらさ」を感じやすい部分もあります。
特に在職中の転職活動では、窓口手続きや開庁時間の都合で利用が難しくなることもありました。
良くも悪くも、ハローワークは「現在働いていない人」や「ブランクがある人」向けに組み立てられている印象です。
私にとっては「0→1の就職活動」では心強い存在でしたが、次のステップを考えたときには、別の手段を選ぶことにしました。
ハローワークと転職エージェントの使い分け


ハローワークと転職エージェント、それぞれに強みと弱みがあります。両方を利用してみて、「どんな場面でどちらを使うか」を使い分けが大切だと感じました。
ハローワークは、就職が初めての人や、ブランクからの復帰を目指す人にとって心強い支援があります。
専門援助部門や支援機関との連携など、サポート体制の安心感が大きなメリットです。
一方で、在職中の転職活動やキャリアアップを目指す場合は、転職エージェントのほうが動きやすいと感じました。
求人の選択肢が広がるだけでなく、応募手続きや日程調整も代行してもらえるので、就活の負担が大きく減ります。
「どちらを使うか」で迷うかもしれませんが、どちらか一方に絞る必要はありません。就職活動のタイミングごとに、サービスを使い分けながら進めていくのも有効です。
自分の状況に合わせて、「今はどちらが使いやすいか」を判断することが、無理なく動くコツだと思います。
≫【結論:両方】障害者雇用の転職はエージェントとハローワークどっちを使う?
まとめ|ハローワークの障害者支援は人によって有効
この記事では、発達障害のある方がハローワークを利用するうえでの支援や注意点について、実体験をもとに紹介しました。
- 専門援助部門で定期的な面談が受けられる
- 地域密着の求人や支援と連携して進められる
- 条件や状況によっては使いにくさもある
ハローワークの支援は、人によって合う・合わないがあります。気になる方は一度相談してみて、自分にとって合うかどうか確かめてみてください。


発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?
- 自己分析が進まない → 自分の強みが分からない
- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない
- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配
こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼りましょう!
- 書類添削+面接対策で合格率UP
- 特性に合う求人を一緒に選べる
- 日程調整や企業とのやりとりを代行
もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?



方向性の相談だけでもOK。初めてなら「dodaチャレンジ」がオススメだよ!
\ 発達障害の当事者が厳選! /